救助隊の活動についてこの記事を読んだらわかること

今回は、消防隊による人命救助活動の際の建物の破壊(処分)行為についてレポートします。破壊行為というと、乱暴に聞こえるかもしれませんが、人命検索の場においては、判断を迫られることがあります。重要なポイントは次の2つです。
この2点がポイントになっています。それでは、詳しく説明します。
火災時の人命救助活動における建物の破壊(処分)行為は認められている

一般の人が、他人の所有物を損壊、破壊すると、刑法第261条に定められた器物破損罪が適用され、罰せられます。これは、法律に規定されているため、日本に住んでいる人は全員対象です。
では、消防士についてはどうでしょうか。119番通報があったとします。隣の一戸建ての住宅用火災警報器が吹鳴しており、煙が充満しているとの通報です。出動します。通報者に接触します。通報者によると、玄関や窓には鍵がかかっていて、中の状況は確認できないようです。
家人は、出かけるときはいつも車だそうです。車は駐車場に停まっています。家の中にいる可能性は非常に高そうです。近所に、家の鍵を持っていそうな親せきなどはいないか確認しても、独り身で親せきはいないそうです。
このような場合、消防隊は、破壊行為の判断を迫られます。状況的に、選択肢がなかったため、リビングの掃き出し窓を破壊し、人命検索を行いました。しかし、家の中に家人はいません。すると、家人が徒歩で帰ってきました。
家の中では、なんとバルサンが焚かれています。そうです、誤報です。さぁ、困りました。家人としてはいい迷惑ですよね。家中のゴキブリやダニを殺してやったぜと、意気揚々と家に戻ったら、消防車がたくさん来ており、家の窓は割られているわけです。
ふざけるなと怒り狂っても仕方ありません。家人は言います。

何をやっているのだ!勝手に人の家を壊しやがって!
器物破損罪で訴えてやる!壊した窓も弁償しろ!
はい、ここで、本題に戻ります。火災における緊急措置(使用、処分、制限)や費用負担については、消防法第29条に規定されています。
消防法第29条(消火活動中の緊急措置等)
消防吏員又は消防団員は、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のために必要があるときは、火災が発生せんとし、又は発生した消防対象物及びこれらのものの在る土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。
② 消防長若しくは消防署長又は消防本部を置かない市町村においては消防団の長は、火勢、気象の状況その他周囲の事情から合理的に判断して延焼防止のためやむを得ないと認めるときは、延焼の虞がある消防対象物及びこれらのものの在る土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。
③ 消防長若しくは消防署長又は消防本部を置かない市町村においては消防団の長は、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のために緊急の必要があるときは、前二項に規定する消防対象物及び土地以外の消防対象物及び土地を使用し、処分し又はその使用を制限することができる。この場合においては、そのために損害を受けた者からその損失の補償の要求があるときは、時価により、その損失を補償するものとする。
④ 前項の規定による補償に要する費用は、当該市町村の負担とする。
⑤ 消防吏員又は消防団員は緊急の必要があるときは、火災の現場附近に在る者を消火若しくは延焼の防止又は人命の救助その他の消防作業に従事させることができる。
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
今回の事例でいうところの窓の破壊、つまり破壊行為というのは法文中の「処分」に含まれています。この法文を簡単にいうとこうです。
と、いうものです。先ほどの家人の要求は2点ありました。
- 器物破損で訴える
- 壊した窓を直せ
消防本部がとるべき対応は明白です。1番については、法律で認められている行為なので違法性がありません。
(正当行為)
第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
(緊急避難)
第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
② 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
刑法より引用
2番については、窓を直す必要があります。窓を直すお金は、その消防本部を運営している市町村町の税金です。そのため、窓の破壊に至るのは、あくまでも最終手段です。それまでには次のようなことを試します。
今回紹介した事例は緊急性がないと判断される事例です。
- 実際に火災が発生した状況
- 社会通念上、緊急性が高いと判断される状況
このような場合は、消防法第29条第3項には該当せず、補償の必要はありません。
なお、今回の事案のような判例が見つかったので以下に記載します。興味深い内容です。
主文
- 原告の請求を棄却する。
- 訴訟費用は原告の負担とする。
文 事 実 及 び 理 由
第1 当事者の求めた裁判
1 請求の趣旨
- 被告は,原告に対し,41万8824円及びこれに対する平成18年1 1月30日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
- 訴訟費用は被告の負担とする。
- 仮執行宣言
2 請求の趣旨に対する答弁 主文と同旨
第2 事案の概要
1 本件は,原告が普通乗用自動車(以下「原告車両」という。)を運転中,先 行する複数の車両に轢かれた交通事故被害者(以下「本件事故被害者」とい う。)を更に轢き,その体の一部がその底部にからみついたので,これを除去 回収するため,被告により設置されたA消防署A特別救助隊等に所属する救助 隊員らが,救助工作車のクレーンを使用して原告車両を持ち上げた際,同車両 に変形等の損傷を与えたとして,国家賠償法1条1項に基づき,被告に対し, 車両の修理費41万8824円及びこれに対する不法行為の日である平成18 年11月30日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求め た事案である。
2 前提事実
以下の事実は,争いのない事実又は証拠(甲1ないし4,甲6,乙1,乙5 ないし7,乙8の1ないし8,乙9,乙10,証人D,原告本人)及び弁論の 全趣旨により容易に認められる事実である。
(1) 当事者
ア 原告
原告は,登録番号熊谷○○×△△△△の原告車両(BMW)を所有して いる。
イ 被告
被告は,宮城県内の市町村のうち, ,b,c,d, ,,g, 及び a e f h i によって構成され,仙南地域広域行政事務組合規約3条4号に基づき,消 防組織法及び消防法の規定による消防事務に関する事務処理権限を持つ地 方自治法1条の3第3項の地方公共団体の組合である。 A消防署A特別救助隊,同署A分隊及びB消防署B救助隊は,仙南地域 広域行政事務組合特別救助隊等設置規程2条1項に基づき,被告により設 置された救助隊である。
(2) 死体の轢過,原告による通報及び救助隊の出動
ア 死体の轢過と原告による通報
(ア) 原告は,平成18年11月30日午後7時20分ころ,原告車両を a 運転し,宮城県内の国道○号線を 方面に向かってその供述によれば時 速約45キロメートルの速度で進行中,宮城県B郡A町××先路上(以 下「本件事故現場」という。)において,進路前方約40メートルの地 点に黒色様の障害物(後に判明したところによれば先行する複数の車両 に轢かれた本件事故被害者の体躯)を発見したが,停止することなくこ れを轢過した。
(イ) 原告は,本件事故被害者の体躯を轢過した直後,車両底部に何かが 引っかかった感じを受け,同車両を停止させて見てみると,車両の下に 人の足の一部が見えたことから,人体を轢過したことを知り,110番 通報をし,同日午後7時27分ころ119番通報をした。
イ 救助隊の出動
被告の指令課は原告の通報を受け,これに基づく出動命令により,A消 防署A特別救助隊及び同署A救急隊が同日午後7時33分ころ,B消防署 B救助隊が同日午後7時36分ころ,A消防署A分隊が同日午後7時37 分ころ,それぞれ本件事故現場に到着し,特別救助隊員6名,救急隊員3 名が救助工作車1台,救急車1台,ポンプ車1台及びその他の車両(搬送 車など)4台の装備で,警察官10名と共に救助活動に当たった(以下, 上記の各救助隊等を総称して「本件救助隊」という。)。
( 3) 死体回収作業と原告車両の破損
ア 死体の発見
本件事故現場に臨場した本件救助隊の隊員らの確認により,本件事故被 害者は既に死亡しており,その衣服と内臓の一部が原告車両の排気管に巻 き付くなどし,その死体が原告車両底部に深くからみついていて容易に除 去することができないことが判明した。 しかも,本件事故被害者の手足が折れ曲がって白煙を上げ,本件事故現 場周辺には,その血液や脳漿その他身体組織片が散乱して,人肉が焦げる 音と臭気が広がっており,同現場周辺に集まった人たちからは,「早く出 してやれ」などの声があがっていた。
イ マイティバックの使用
本件救助隊の隊員らは,原告車両底部に深くからみついた本件事故被害 者の死体を回収するため原告車両前部を持ち上げる作業として,まず,常 備していたマイティバックと呼ばれるマット型空気ジャッキを原告車両の エンジン下に挿入する方法(車体と地面の間にバックを入れ,バックに空 気を入れることによって空気圧により車体を持ち上げる方法)を試みたが, この方法によっては,車体を30センチメートル程度持ち上げることがで きたにとどまり,車両底部にからみついた死体を取り出す作業に必要な空 間を確保することができなかった。また,本件救助隊は,装備している油圧式ジャッキや角材等を用いて車 体を持ち上げる方法も検討したが,不安定であり,作業に当たる救助隊員 の身に危険の及ぶおそれがあり,不適当と判断した。
ウ クレーンによる持ち上げ作業の実施
(ア) そこで,本件救助隊は,救助隊所属の救助工作車(2.9tのユニ ッククレーン車。以下「本件救助工作車」ともいう。)に設置されたク レーンを用いて必要な作業空間を確保することとし,原告車両の前部の 左右ロアアームの下に被覆ワイヤーを掛け,ワイヤーの両端を1点で救 助工作車に設置されたクレーンの先端に取り付けて,原告車両の前部を 持ち上げ,本件救助隊員が原告車両の下に身を入れてその底部に深くか らみついた死体の一部を漸く取り外すことに成功した。本件救助隊員は 取り外した死体を毛布に包んで救出した。
(イ) 原告は,その作業に先立ち,現場にいた警察官から,その死体の取 り外しのために原告車両を持ち上げる旨告げられ,これに同意した。本 件救助隊の隊員らは,持ち上げ作業に先立ち,原告に対し,本件救助工 作車のクレーンにより持ち上げるという方法を採ること及び同方法によ り原告車両が破損する危険性があることを説明しなかった。
(ウ) 本件救助隊の救助工作車による持ち上げ作業により,原告車両の左 右フェンダー部分がひしゃげたような変形が生じた。原告は,この修理 のため,40万円程度の費用を要した。
3 争点
- 救助工作車による原告車両の持ち上げ作業の違法性
- 原告車両の損害の程度
4 当事者の主張
(1) 争点(1)(違法性)について
ア 原告の主張
(ア) 本件救助隊の隊員らが本件事故現場に臨場した際,本件事故被害者 は既に社会死状態にあったのであるから,原告車両の持ち上げ作業を行 うに当たっての緊急性は低く,原告車両を破損してまで緊急に同被害者 の死体を回収する必要はなかった。したがって,本件救助隊としては, 原告車両に損傷を生じさせない他の持ち上げ方法を採用するか,同車両 の本件救助工作車による持ち上げと車両破損の可能性について原告に説 明の上その承諾を得るべきであった。 なお,原告は,車両を持ち上げることについては同意したが,車両の 破損についてまで同意したものではない。
(イ) 原告車両に損傷を生じさせない他の持ち上げ方法として,例えば, 本件救助隊が救助工作車による車両持ち上げ作業に着手した時点で,既 にレッカー業者である有限会社Cのレッカー車が臨場していたのである から,同レッカー車により2点吊りにて持ち上げ作業を行えば,原告車 両の破損は生じなかったはずである。 また,仮に,同時点でレッカー車が到着していなかったとしても,本 件救助隊が原告車両を破損しない他の手段を検討したのであれば,警察 官の手配したレッカー車が臨場することが判明し,あるいは,警察官や 原告にレッカー車や車両積載車の手配を依頼することもできたのであり, レッカー車等の臨場を待って,車両持ち上げ作業をすることも可能であ った。
イ 被告の主張
(ア) 特別救助隊を含む救助隊は,消防法1条及び消防組織法1条により 災害による被害の軽減,すなわち災害救助の職務を担っているところ, 本件事故現場において救助工作車により原告車両を引き上げ,本件事故 被害者の死体を回収した行為は,緊急避難ないし緊急状況下における救 助隊としての正当な業務行為であり,違法性はない。すなわち,本件救助隊の隊員らは,惨状を衆目に晒したままの本件事 故現場を一刻も早く旧に復す必要に迫られ,死者に対する尊厳を急ぎ回 復するため,緊急避難として,本件事故被害者の死体の損壊と原告車両 の毀損のうち,より重大な法益侵害である死体の損壊を回避したのであ り,あるいは,本件事故被害者が車両引き上げ作業の時点では既に社会 死状態にあったといっても,凄惨な本件事故現場において,その死体を 一刻も早く収容するといった作業も,救助隊の任務である災害救助に含 まれる人命救助と密接不可分の関係にあるものとして,救助隊の正当な 業務に含まれるものである。 なお,本件事故現場において,原告車両を持ち上げるに当たり,他の 方法を採ることは不適切あるいは不可能であった。
(イ) 事故車を移動するためのレッカー車は,費用負担や二次災害の防止 といった観点から,一連の救助作業が終了した段階で,当事者に確認の 上警察官がレッカー業者に臨場を要請するもので,本件救助隊の隊員ら が原告車両の持ち上げ作業に着手した時点では,Cのレッカー車は本件 事故現場に臨場していなかった。 また,上記のとおり,死体の収容も救助隊の任務の一つであるところ, 救助隊が,急を要する死体収容作業を放棄し,民間のレッカー業者の臨 場を待つことは許されない。
(2) 争点(2 )(損害)について
ア 原告の主張
本件救助隊の救助工作車による持ち上げ作業によって,原告車両の左右 フェンダー部分に変形が生じ,また,作業中の救急隊員の乱暴な扱いによ りフロントドア内側レバーが破損し,原告車両に修理費41万8824円 の損害が発生した。
イ 被告の主張
救助工作車による持ち上げ作業によって,原告車両の左右フェンダー部 分に変形が生じたことは認めるが,責任については争う。フロントドア内 側レバーの破損については知らない。
第3 当裁判所の判断
1 争点( 1)(違法性)について
( 1) 上記のとおり,被告は,消防法及び消防組織法の規定による消防事務に 関する事務処理権限を持つ地方公共団体の組合であり,その権限に基づき本 件の作業を行った本件救助隊を設立したものである。 消防法は,その目的として,災害による被害を軽減し,社会公共の福祉の 増進に資することを掲げ(1条),人命の救助を行うため必要な特別の救助 器具を装備した消防隊(救助隊)を配置することとしている(36条の2)。 また,消防組織法は,消防は災害を防除しこれによる被害を軽減することを 任務とするものと定めている(1条)。そして,消防法36条の2の規定に 基づき救助隊の編成,装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省 令第22号,以下「本件省令」という。)は,救助隊は人命の救助に関する 専門的な教育を受けた隊員で編成され,救助器具及びこれを積載することが できる救助工作車その他の消防用自動車1台を備えるものと定めている(2 条)。こうした救助隊の設置の目的及び任務に照らせば,その職務は公共の 利害に関わり,かつ公益の目的に奉仕するものであることは明らかである。 そして,消防法及び消防組織法の定める上記のような目的及び任務に鑑み れば,救助隊の職務には交通事故による被害者の救助等その生命身体の保護 を含むことはもとより,不幸にして救助に至らずあるいは既に死亡してしま った被害者についてその死体等を適切に処理することも,救助活動に通常随 伴し,またこれと密接な関係にあるものとして,その職務の内容に包含され るものと解するのが相当である。 また,救助隊のこのような職務の内容及び性質に照らせば,被害の回復除去等のその職務遂行の過程において,ときに他人の生命身体の安全やその他 の重大な法益に対する差し迫った危険等を除去するための緊急の必要から, 被害者以外の者の所有権等の私的権利を侵害する措置に及ぶことを余儀なく される場合も当然に予想されるところ,このような災害防除のための消防活 動の一端を担う救助組織が公共の福祉に資する目的の下に法令上定められて いる法意に鑑みると,こうした救助組織の活動による法益侵害行為について は,その行為の態様とこれにより侵害される法益の性質や程度等を考慮の上 で,それが救助の目的,範囲を著しく逸脱しているとか,救助活動に関する 権限を濫用するものであると評価すべき特段の事情があるというような場合 は格別,そうした事情の認められない限りは,その救助活動は,法令に基づ く正当な職務行為として,国家賠償法1条1項の違法性が阻却されるものと 解するのが相当である。
( 2) 本件においては,本件救助隊は,原告が誤って死体を轢過したことから, その通報により出動したところ,既に被害者は死亡していたがその死体の一 部が原告車両の底部にからみついていたことから,現場に臨場した救急部隊 としてその処理の掌に当たったものである。 ところで,現場は一般国道上であり,道路上には被害者の死体の一部が散 乱し,原告車両の底部には死体の一部が深くからみつき,焼けこげる臭いが 周囲にたちこめるという凄惨な状況にあったものである。こうした状況の下 では,現場に臨場した本件救助隊としては,速やかに現場の交通の安全を確 保しつつ,災害被害者である死者の尊厳を保ちながら適切な方法をもって遺 体の収容に努めること(なお,遺体の処理方法によっては死体損壊の罪に該 当するおそれがある。)が強く要請されるものであるところ,原告車両を移 動させることによる更なる死体の損壊を防ぐためには,当該現場において, 可能な限り速やかにこれを除去し保全を図る必要があると判断すべき状況に あったのである。そこで現場での死体除去の作業のためには死体を轢過した原告車両をその場で持ち上げた上で救助隊員がその下に潜るような体勢で作 業をする必要があるところ,本件救助隊が装備していたエアマットでは原告 車両の前部を充分に持ち上げることができず,また,角材その他の道具を使 用して持ち上げる方法では自動車の重量を考えると不安定な体勢での作業を 強いられることとなり,作業に当たる本件救助隊員の生命身体に危険を及ぼ すおそれがあるため,いずれも相当な方法とはいえない。そこで,本件救助 隊が装備する本件救助工作車のクレーンを使用して原告車両を持ち上げる方 法こそが上記のような難点を克服するものであり,その場合に,原告車両に 対する損傷の程度をより少なくする方法として,そのフェンダー部分に被覆 ワイヤーをかけて持ち上げる方法が当時の現場において即時に採り得る手段 として相当なものと評価することができる(なお,原告は当時現場に臨場し た警察官に対して死体を轢過した原告車両を持ち上げることに同意をしてい たという事情があるところ,上記の方法を用いた場合であっても,原告車両 を持ち上げるからには,その作業に当たり必然的になにがしかの損傷が生じ る可能性のあることは容易に想到し得るところであるが,自ら死体を轢過し た結果生じた事態を適正に処理するために採るべきやむを得ない措置の結果 生じたものであれば,一般に甘受せざるを得ないものと受け止められるとこ ろではないかと思われる。)。本件救助隊が採用した持ち上げの方法により, 所期した目的は達成したものの,この過程で原告車両の左右フェンダー部分 が変形する損傷(修理費として約40万円を要する程度のもの。)が生じる こととなったのであるが,こうした損傷の程度態様を考慮しても,こうした 損傷が生じることとなった経緯を踏まえて本件救助隊が採用した方法につい て検討してみると,当時の救助現場における救助の必要性及び緊急性等の諸 般の事情に照らせば,それが救助の目的,範囲を著しく逸脱したものである とは到底認めることができないし,こうした方法を採用したことについてそ の権限を濫用するなどの特段の事情があるともいい難い。したがって,上記方法による原告車両の持ち上げ行為は,本件救助隊の正当 な職務行為として違法性が阻却されるものというべきである。
( 3) これに対し,原告は,被害者は既に死亡しているため,原告車両の持ち 上げは緊急の要請とはいえなかったとして,業者に対してレッカー車の出動 を要請してこれを使用すべきであり,そうすれば原告車両には損傷が生じな かったと主張する。 しかしながら,本件現場における上記判示の状況に照らすと,道路交通の 安全確保及び死体の尊厳に配慮した処理の観点からしても,人命それ自体の 救助の場合の緊急性に比べればその切迫の度合いこそ劣るとはいえ,依然と して可及的速やかな処置が強く要請されていたことに変わりはなく,現場に おける緊急処理を要する作業であることは明らかであった。そうであれば, 本件救助隊が自ら装備していない(証拠(乙5)によれば,本件省令上も常 備すべきものとはされていない。)レッカー車の使用を選択すべきであった とはいえず,ましてその手配を要請しその到着を待つべきであったなどとは いえない。なお,原告は,当時現場には警察官の要請によりCのレッカー車 が到着待機していたから,これを使用して救助に当たるべきであった旨主張 し,証拠(甲6,原告本人)中にはこれに沿う部分があるが,こうした要請 による待機の事実自体を否定するCの代表者の陳述書(乙9)並びに証人D の陳述書(乙10)及びその証言と対比するとにわかに採用することはでき ないから,その前提において失当というべきであるし,そもそも本件救助隊 において当時レッカー車がすぐに使用できる状態にあったことを認識してい たような事情も認められないから,いずれにせよ,原告の主張は理由がない。 また,原告は,車両損傷の可能性について本件救助隊は原告に対して事前 に説明の上その承諾を得るべきであったとも主張するが,処理の必要性及び 緊急性と原告車両に加えられる可能性のある損傷の程度態様に照らせば,そ うした説明及び承諾を欠いたからといって,直ちにその職務行為の違法性の阻却が認められないものとはいえない。
(4 ) 原告は,本件救助隊の隊員らの救助作業中に原告車両のフロントドア内 側レバーが破損したと主張するところ,原告車両のそうした破損のあること は証拠(甲2)により認められるが,それが本件救助隊の隊員らの救助作業 中に生じたと認めるに足りる証拠はない。
2 結論
以上によれば,その余の点を検討するまでもなく,原告の請求は理由がない ことが明らかであるから,これを棄却することとし,訴訟費用の負担につき民 事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
さいたま地方裁判所 第6民事部
水災時の人命救助活動における建物の破壊(処分)行為についてはどうだ?

火災時は、先ほどの消防法第29条により、器物破損罪にはなりませんでした。では、台風による大雨などで、洪水があった場合はどうでしょうか?
洪水があったため、消防隊がボートで救助活動に向かったとします。1階はすべて浸水していますが、2階はまだ浸水していません。生存者のいる可能性があります。しかし、2階の窓には鍵がかかっており、人命検索ができません。2階のベランダには洗濯物が見えるため、空き家でないことは確かです。
窓を破壊して、2階に侵入し、屋内検索を実施します。階段の途中まで水没しているため階段下の人命検索はできませんが、とりあえず2階には誰もいません。後からわかったことですが、どうやら家人は、泥棒が入らないように家の戸締りをして、台風に備え高台の公民館に避難していたようです。台風が過ぎさり、数日たち、水位が下がります。家人が家に帰ります。
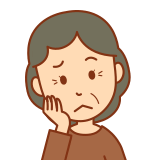
1階は水没して使い物にならないな。
とりあえず浸水は免れた2階で過ごして、1階の復旧作業にかかろう ・・・
しかし、浸水していないはずの2階の窓は割られ、誰かが侵入した形跡があります。割れている窓の前には足場がないため、空でも飛べない限り、この窓から人は入れません。そこで家人は気づきます、洪水時にボートに乗っていた消防隊が割ったに違いない。
窓を弁償してもらおう。先ほどの、火災の事例と同じような状況です。これが火災なら、消防法に根拠があり
というものでした。しかし、災害種別が違います。消防法第29条には、「消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のために緊急の必要があるときは、・・・」と書いてあります。今回のような洪水、大きい意味では水による被害ということで水災ですね、水災については書いていません。
さらには、消防法第36条第8項に次のように書かれています。
消防法第36条第8項
第18条第2項、第22条及び第24条から第29条まで並びに第30条の2において準用する第25条第3項、第28条第1項及び第2項並びに第29条第1項及び第5項の規定は、水災を除く他の災害について準用する。
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)
準用、準用と、何を書いているのかさっぱりわかりませんね。要約すると、消防法第29条に書いてあった
というルールは、水災以外の災害にも使っていいよ!というものです。

え?水災だけ、どうしてわざわざ消防法の規制から外しているの?
理由は、水災に関する内容は、昭和24年に制定された水防法に規定されているからです。ということは、消防は、壊した窓を修理するだけでなく、器物破損罪でも訴えられてしまうのでしょうか。答えは、NOです。理由は次のとおりです。水防法の規定を解釈することで理解できます。
✔️消防学校とは ✔️初任科の内容 ✔️初任科のカリキュラム ✔️初任科の準備(荷物編) ✔️初任科の準備(暗記編) ✔️初任科の準備(事前勉強編) ✔️初任科(勉強以外) ✔️初任科以外の入校
救助要請について「水防法」における規定

水防法第28条に、緊急措置についての記載がります。
水防法第28条(公用負担)
第二十八条 水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防の現場において、必要な土地を一時使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは収用し、車両その他の運搬用機器若しくは排水用機器を使用し、又は工作物その他の障害物を処分することができる。
② 前項に規定する場合において、水防管理者から委任を受けた者は、水防の現場において、必要な土地を一時使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、又は車両その他の運搬用機器若しくは排水用機器を使用することができる。
③ 水防管理団体は、前二項の規定により損失を受けた者に対し、時価によりその損失を補償しなければならない。
水防法(昭和24年6月4日法律第193号)
消防法と同じく難しいことが書いてありますが、3つの解釈の工夫をすることで、答えが出ます。
- 人命救助を目的とする旨の記載はないが、水防活動の際における人命救助は、水防法が究極的には人命の保護を目的とするものであるから、水防の範囲に含まれると解される。
- 「水防のため緊急の必要があるとき」とは、洪水、雨水出水、津波又は高潮により堤防等が決壊の危険にさらされており、その区域の水防管理団体の人員及び資材をもって水防活動を行うのみでは防護することが困難であると認められる場合等をいう。
- 「工作物その他の障害物を処分することができる」とは、水防に支障のある家屋その他の建築物、施設、立竹木等の物件を破壊したり除去したりすることである。
この3点から、水災時における人命救助等のために行う緊急的な建物の破壊行為については、消防法上の規定はないが、水防法第28条を根拠に行うことが可能であると解釈できます。したがって、先ほどの事例においても火災と同じように
という対応が正解となります。
消防法29条|破壊救助を根拠と共に徹底解説|救急隊が窓破壊?のまとめ

消防は、火災のときでも、水災のときでも、人命救助のために、緊急の必要があれば、建物を壊すことができるものの、壊された人から直してと言われたら、直す責任があることが良くわかりました。
壊された人から直してと言われたときに、直す必要があるかどうかのポイントは、緊急の必要性があるかどうかということになります。
ただ、法律上はこのようになっているものの、現実的には消防機関に対して弁償を求める市民は少ないようです。人命救助のために行った行為ということもあり、人間心理が働くためだと考えられます。
今後も、新しい情報が入り次第、レポートを更新していきます。
この記事を読まれた方で、さらに詳しく知りたいことがあれば追跡調査しますので、コメントか問い合わせフォーム、またはTwitterにてご質問ください。
また、消防関係者の方で、うちの本部ではこうなってるよ、それは違うんじゃない?などのご意見をいただける際も、コメントか問い合わせフォーム、またはTwitterにてご連絡いただけると助かります。
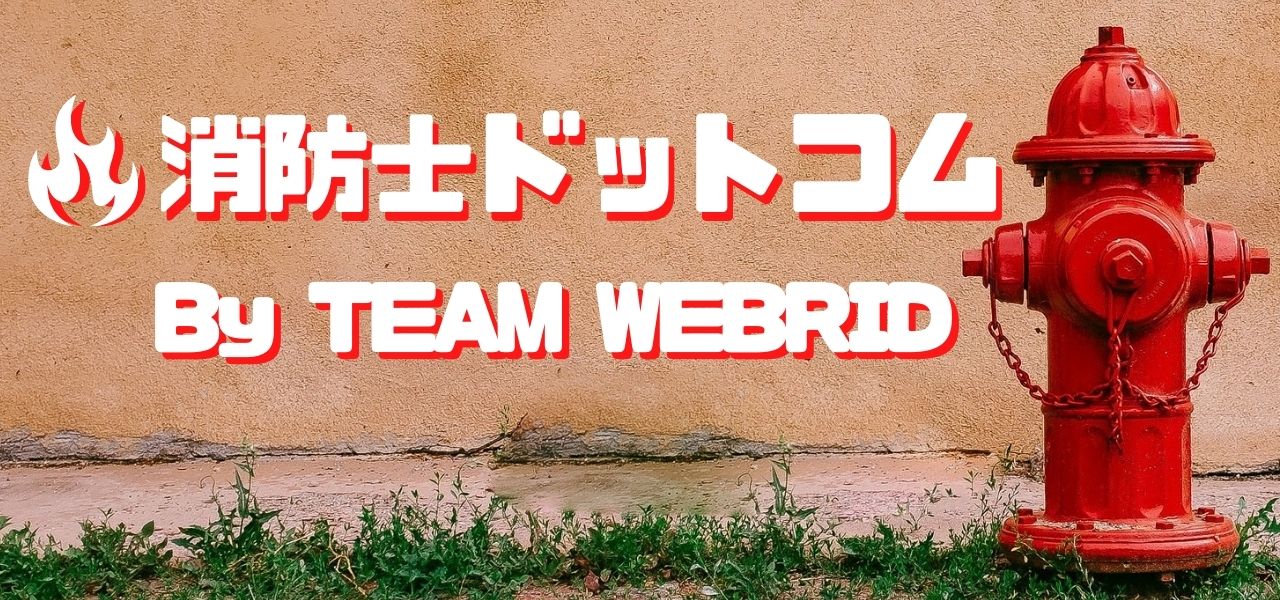

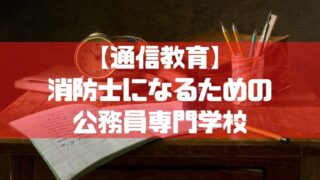









の違い-320x180.jpg)
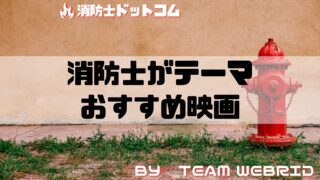












コメント
「救助要請!ドアには鍵!」
の記事の中で、著者は
「人命救助活動における建物破壊が誤報によるものであった場合、
建物を直す必要があります。直すお金は、その消防本部を運営している市町村町の税金です。」と説明されています。
現実の地方公共団体の判断はこのとおりでしょうか?
著者は現実の消防局の責任者の判断を確認したことはありますか?
次は実際に発生した案件です。
誤報による建物破壊行為について、下記の各部署に損失補償を請求したところ、
いずれも、「消防法29条第一項に該当するので、消防法29条第三項には該当せず、従って損失補償はしない、修繕費用は払えないという判断に固執し続けています。
「人命救助活動における建物破壊が誤報によるものであって結果的に災害が発生していなかったことが明らかになったとしても、119番通報に基づき出動したことに正当性があるので、破壊された建物は[災害が発生した]119番活動の対象物で処分することができる」との理由を主張されてしまいました。
誤報により破壊された建物は消防法29条第一項に規定されている消防対象物であり、第一項と第三項は互いに排他事象であるので、第三項の損失補償とならないと判断していると主張されてしまいました。
横浜市消防局中消防署長
横浜市長
横浜市消防局長(消防長)
横浜市消防局総務課
著者のご意見を求めます。
杉本様
非常に興味深い情報提供ありがとうございます。
この件については、詳しくリサーチさせていただきます。
リサーチ後、改めて記事の加筆修正等に進めさせていただきます。
その際には、こちらの記事への変身にて回答させていただきますので、よろしくお願いします。
TEAM WEBRID 御中
早速のご返信ありがとうございます。
詳しくリサーチされ、その後このコメントにご返信されるとのこと、お待ちしております。
リサーチの助けになる事実関係の証拠として、
行政文書開示請求(個人情報本人開示)によって横浜市長が一部開示決定し中消防署から入手した「×年×月×日に〇〇に出場した件についての中消防署長への報告書」、および私から横浜市消防局長あての損失補償しない理由説明の求めに対し受け取った、代理担当者からの回答文書を提供する用意があります。
登録しました私のアドレスあて著者またはTEAM WEBRIDのメールアドレスを通知いただければPDF化した文書をメール返信にてファイル添付いたします。
杉本さま
貴重な情報提供ありがとうございます。
では、TEAM WEBRID広報担当者のメールアドレス
ginteamwebrid@gmail.com
こちらまで資料提供いただけたらと思います。
お預かりした資料につきましては、モラルある管理とさせていただきます。
よろしくお願いします。
TEAM WEBRID 御中
ただ今、ご指定先に送付いたしました。リサーチください。
一点、お送りいただいた資料の中で確認したいことがあり、指定のアドレスへ送信しています、ご確認ください。
杉本さま
ご連絡いただいたメールアドレスに考察結果を送信しております。
ご確認ください。