
消防士の採用試験に受かったものの、消防学校の生活が不安です。
こんな不安を解消する記事となっています。この記事では、消防学校での生活のようすについて、【消防学校の情報】よりもさらに詳しく”初任科”に注目してレポートします。消防学校って、未知の世界で不安ですよね。この記事を読むことで、消防学校の生活がイメージでき、不安が和らぎます。今回の記事も、現役消防士や消防職員OBへの取材をもとに説明します。それでは、レポートします。
- 消防学校の初任科の期間はどれぐらい?
- 消防学校入校中も給料がもらえる?
- 消防学校は入校式に始まり、終了式で終わる
- 消防学校は班単位の行動が基本
- 消防学校での生徒の呼ばれ方は「〇〇学生」
- 消防学校の先生役の立場は「教官」
- 消防学校の成果は成績で順位が決まり、成績優秀者や班は表彰される
- 消防学校には多くの当番がある
- 消防学校の1日のスケジュール
- 消防学校の外泊は金曜日の17時から日曜日の21時まで
- 消防学校は週に一度、夕食後から21時まで外出できる
- 消防学校では就寝中の出動訓練がある
- 消防学校でも喫煙は可能
- 消防学校の食事はセルフサービス
- 消防学校の洗濯は洗濯機や乾燥機
- 女性も男性同様に消防学校に行く
- 消防学校|初任科を15項目で解説|総代や教官になるにはのまとめ
消防学校の初任科の期間はどれぐらい?

消防学校の初任教育である”初任科”の期間は全国的に共通して6か月です。警察学校は、採用区分(大学卒・高校卒の違いなど)によって、6か月から9か月と違いがあるようですが、消防学校の場合は採用区分による教育時間の違いはありません。珍しいところでは、初任教育である”初任科”と、救急隊員の資格を取得するための”救急科”(卒業に2か月必要)を合わせて8~9か月程度の初任教育を行う場合もあります。
消防学校入校中も給料がもらえる?

学校に行きながら給料が貰えるなんて嘘みたいですよね。今までは高校や大学にお金を払って勉強させてもらっていたはず。うわさに聞く、「消防学校に行きながら給料がもらえる」ということは嘘なのでしょうか?
いえいえ、【消防学校の情報】でも話したとおり事実なのです。そのカラクリを説明します。みんなが違和感を持つ最大の理由は、「学校」という名前がついているから。他の言い方をするならば、研修所です。あなたは、採用された消防本部から、採用されて早々に長期の出張を命じられるわけです。出張先は、消防学校という名の研修所です。
つまり、身分は「学生」ではなく、あくまでも消防本部に採用されている消防士。だんだん見えてきましたね。消防学校に入校中の給料は、もちろん採用された消防本部から支払われます。では、消防学校の学費は誰が支払うのか?
もちろん、あなたを採用した消防本部です。消防本部は、新たに採用した消防士を教育するため、消防学校に研修に必要な費用を支払います。これは、一般企業が社員に対し、経費をさいてスキルや資格を学ばせることと同じことですね。これが、学校に通いながら給料が貰えるカラクリです。
消防学校は入校式に始まり、終了式で終わる

出張という大義名分のもと、都道府県の施設である消防学校へ、都道府県内の複数の消防本部から新人たちが集まります。大きな消防本部では、1つの消防本部単独で消防学校を持っています。学校という名前がついているものの、一般企業でいうところの研修施設です。
学校なので、初日には入校式があります。終了時には、卒業式ではなく終了式があります。卒業の場合は、二度とその学校へ行くことはないと思いますが、消防学校の場合、あくまでも“初任科”という研修を修了しただけです。初任科卒業後も、救急科や救助科などの研修で改めて入校するため、卒業ではなく終了という表現になっています。
消防学校は班単位の行動が基本

初任科は、班単位で動くことが基本です。訓練などのグループ分けも班ごとに分かれます。連帯責任というものを学びます。共同生活を行う寮も班ごとの共同部屋です。6か月間、生活や苦楽をともにすれば仲良くなります。もちろん逆もあります。初任科卒業後も定期的に飲み会を続ける人たちもいます。
消防学校での生徒の呼ばれ方は「〇〇学生」

学校なだけあって、呼び方は「〇〇(苗字)学生!」というのが基本。もちろん、通常会話では、普通にあだ名や名字を呼び捨てにするものの、全体行事の際や訓練中などは「〇〇学生、前へ!」などと呼ばれます。このあたりは県ごとの文化の違いが顕著に現れます。自分が出張を命じられた消防学校の文化に合わせてください。
このような言い方をすると、消防学校を選べるかのように聞こえるかもしれませんが、選べません。
採用された消防本部が、独自に消防学校を運営していれば、自分が採用された消防本部が運営する消防学校に派遣されます。採用された消防本部が独自に消防学校を運営していなければ、都道府県が運営している消防学校へ派遣されます。比較的、政令指定都市のなかでも大規模な消防本部は、消防本部単独で消防学校を運営しています。
消防学校の先生役の立場は「教官」

学校というだけあって、先生役の人がいます。一般企業だと、研修所の講師と呼ぶべきでしょうか。しかし、「先生」とは呼びません。テレビなどでたまに耳にするあれです。そう「教官」です。「〇〇教官」と呼びます。この消防学校の教官というのは何者なのでしょうか。説明します。
消防本部が単独で運営している消防学校の教官
消防本部が単独で消防学校を運営している場合は、想像がつくと思います。悩む要素がありませんよね、そうです、消防学校を運営している消防本部の消防士です。異動で、消防学校の教官に異動します。シンプルですね。次は厄介です。
都道府県が運営している消防学校の教官
都道府県が運営する消防学校の教官は、数パターンの教官がいます。まずは、都道府県の消防学校なだけあって、都道府県の職員がいます。しかし、都道府県の職員というのは、俗に言う行政職として採用された事務職の人です。そのような人たちに消防士の教育ができるのでしょうか。実は、都道府県の消防学校にいる都道府県の職員というのは、元消防士が大半を占めています。
例えば、消防本部で採用されたものの、消防学校から声がかかり、都道府県の職員に特別枠として採用されるパターンがあります。他には、東京消防庁や都会の大きな消防本部に、地元を離れて、若いころ勤めていたものの、諸事情で地元に戻る必要が出た。いざ、地元の消防本部を受け直そうとしたものの、年齢制限にかかり受けることができない。
似た条件の職を探すと、都道府県の職員の採用年齢は消防に比べて高く、受験できることがわかる。そこで、都道府県の職員を受験すると、面接試験で前職の仕事の話が当然出る。履歴書にも前職や経歴は書きますよね。都道府県側としては、不適切な理由で消防を辞めたわけでなければ、
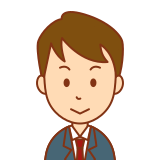
消防学校に勤めさせることができる人材だ、ラッキー!
ということで採用し、教官に異動させます。
また別のパターン。これは、2年ごとや半年ごとなどの期間限定で、都道府県内の消防本部が、現役の消防士を派遣するパターンです。応援のようなイメージですね。結局のところ、わかりやすく言うと、消防学校の教官は、元消防士、現役消防士ということです。
消防学校の成果は成績で順位が決まり、成績優秀者や班は表彰される

消防学校では、定期的に「効果測定」とよばれる「テスト」が実施されます。実技であったり、筆記試験であったり、さまざまな効果測定が実施されます。多い時には週に複数回実施されることもあります。この成績というのは、点数により順位付けをされ、トータルで卒業時の順位が決まります。都道府県によっては、毎回派遣元の消防本部に成績が報告されます。
消防本部によっては、毎週末の帰署報告で成績の報告を求められる場合もあります。終了式においては、成績優秀者は優等生として表彰されます。よくあるパターンは、学生全体の上位10パーセントが優等生として表彰されるパターンでしょうか。もちろん消防学校ごとで仕組みは異なりますが。100人の同期がいれば、10人が優等生として表彰されるということですね。
消防学校には多くの当番がある

共同生活を送るためには、それなりの当番(役割)があります。一般的な消防学校の当番は次のとおり。
| 当 番 | 人 数 | 任 期 |
| 総代 | 1人 | 1週間 |
| 副総代 | 2人 | 1週間 |
| 班長 | 各班1人 | 1週間 |
| 炊事班 | 寮直の班員 | 1日 |
| 日直 | 1人 | 1日 |
| 寮直 | 1人 | 1日 |
当番それぞれの役割をみてみます。
総代
学生の代表者であり責任者です。全体を指揮します。
副総代
総代を補佐します。総代に何か問題が起きた時は、総代の仕事を代行します。
班長
班員の代表であり、責任者です。次のような任務を行います。
炊事班
食事後の後片付けや食堂の清掃を行います。各自が食べた食器などはセルフサービスで片づけることが一般的です。みんなが使うサラダドレッシングや醤油さしを片づけたり、机を拭いたりします。
日直
担当教官の指示を受けて、次のような任務を行います。
寮直
当直教官の指示を受けて、寮直室で次の任務を遂行します。
消防学校の1日のスケジュール

一般的な1日のスケジュールは、次のとおりです。
- 起 床 6:30
- 点呼・清掃 6:40- 7:20
- 朝 食 7:20- 8:00
- 朝 礼 8:30- 8:55
- 授 業 9:00-11:50
- 昼食・休憩 12:00-12:55
- 授 業 13:00-16:50
- 夕 食 17:00-18:00
- 入 浴 18:00-20:00
- 自 習 20:00-21:00
- 日誌の記載 21:00-21:30
- 点 呼 21:40-21:45
- 消 灯 22:00
午前中に座学を行い、午後から訓練を行います。初任科の後半になってくると、1日中訓練ということもしばしば。訓練の内容によっては、時間どおりに訓練が終わらないことも当たり前のように起こります。
消防学校の外泊は金曜日の17時から日曜日の21時まで

全寮制の寮生活ですが、金曜日の訓練が終了したら家に帰ることができます。1週間ごとの出張が終わるイメージですね。その際、自分が配属された消防署に、「帰署報告」ということで、一週間の訓練の報告に寄ることがあります。
帰署報告の時に、配属された所属から連絡事項を受けたり、給与明細を渡されたりします。効果測定があって成績が悪かった場合、その場で指導を受けることもあります。帰署報告が終わると、やっと家に帰ることができます。金曜日の夜と土曜日の夜は、自宅で寝ることができます。しかし、日曜日の夜には、消防学校へ戻らなければなりません。これは、月曜日の朝から始まる業務にスムーズに対応するためです。
✔️消防学校とは ✔️初任科の内容 ✔️初任科のカリキュラム ✔️初任科の準備(荷物編) ✔️初任科の準備(暗記編) ✔️初任科の準備(事前勉強編) ✔️初任科(勉強以外) ✔️初任科以外の入校
消防学校は週に一度、夕食後から21時まで外出できる

消防学校によりますが、訓練が軌道に乗ると、6・7月あたりから、週に一度の外出を認められるようになります。中日(なかび)である水曜日に外出日を設ける消防学校が多いようです。アルコールを飲みに行くのも良し、週の後半に向けてのスポーツドリンクを買うのも良し、各自が自由に行動します。
消防学校によっては、班ごとに冷蔵庫を割り当ててもらえることがあります。たんぱく質を取るために納豆や卵を常備し、食事にプラスして摂取する学生も多く、外出の際に買い足すことが可能です。
消防学校では就寝中の出動訓練がある

消防署勤務が始まると、消防士は24時間勤務であるものの、仮眠時間があります。もちろん、仮眠時間中に出動がかかれば、出動するわけです。消防学校においても、就寝時間中に、突然放送が入り、身支度を整えて体育館に集合するといった訓練を行います。
訓練の事前告知を行い、学生に準備をされては訓練の意味がないので、予告をせずに突然行われる訓練です。職場で必要なことなので、消防学校で訓練を行うことは当然と言えます。
消防学校でも喫煙は可能

教官にももちろん喫煙者はいます。したがって、敷地内のどこかには喫煙所が設けられていることが一般的です。採用されたばかりの新人が入校する“初任科”だけでなく、年配消防士の幹部教育なども行われる消防学校です。
また、消防団員教育も行われます。喫煙所がないと、こういった発言権の強い人たちのストレスが大きくなりスムーズな教育ができません。喫煙者の人は、日曜日の夜から金曜日の夜まで禁煙なのかという不安を持つ必要はありません。
消防学校の食事はセルフサービス

さきほど、当番の炊事班の仕事でもふれましたが、食事は食堂にてセルフサービスです。食事の時間になると、同じ班のメンバーや、仲の良いメンバーと一緒に食堂へ向かい、お盆を持ち、列に並んでおかずやご飯を次から次へとお盆へ乗せます。
ご飯を食べる机は、食べながらコミュニケーションを取れるように大勢で同時に食べることができる机となっています。メニューは、カロリーと栄養がしっかり管理されており、ボリュームがあるため、訓練で疲れていても不満に感じることはありません。
消防学校の洗濯は洗濯機や乾燥機

共同生活を行う寮にはランドリー室が設けられています。多くの洗濯機と乾燥機が並び、班ごとや、2班で1つの洗濯機と乾燥機が割り当てられます。複数の学生が1つの洗濯機で同時に洗うため、活躍するのが大型の洗濯ネット。
それぞれの学生が自分の洗濯ネットに入れて洗濯機に入れて洗えば、同時に複数の学生が洗濯をしてもどれが誰のパンツだと迷うこともありません。入浴後の時間は、洗濯機がフル稼働します。もちろん雨の日は乾燥機もフル稼働。天気が良ければ、学生寮のベランダや屋上などの洗濯物干し場に干すことが一般的です。
女性も男性同様に消防学校に行く

女性消防士だからといって、消防学校に行かなくてよいというわけではありません。男性と同様の訓練や生活を送ります。もちろんプライバシーの配慮はありますから安心してください。寮の部屋も女性専用ですし、トイレやお風呂、使用する洗濯機なども女性専用です。班の編成は、同期の男女比率によってまちまちのようです。女性だけの班を作る場合もあれば、男性の班に一人ずつ女性を振り分ける場合もある。ただ、男女混合班だからといって、寮の部屋が一緒になるわけではありませんので安心してください。
女性消防士についてはこちらの記事でさらに詳しく説明しています。
消防学校|初任科を15項目で解説|総代や教官になるにはのまとめ

今回の記事では、消防学校の生活について、15項目の情報を紹介してきました。これから消防学校へ入る人、将来消防士になろうと思っている人は不安の1つが解消されたのではないでしょうか。消防学校については、他の記事でも情報を解説しています、『消防学校』のカテゴリーからか、下のリンクからご覧ください。
消防学校について基本的な情報はこちらの記事
消防学校についてさらに知りたい人はこちらの記事
今後も、新しい情報が入り次第、レポートを更新していきます。
この記事を読まれた方で、さらに詳しく知りたいことがあれば追跡調査しますので、コメントか問い合わせフォーム、またはTwitterにてご質問ください。
また、消防関係者の方で、うちの本部ではこうなってるよ、それは違うんじゃない?などのご意見をいただける際も、コメントか問い合わせフォーム、またはTwitterにてご連絡いただけると助かります。
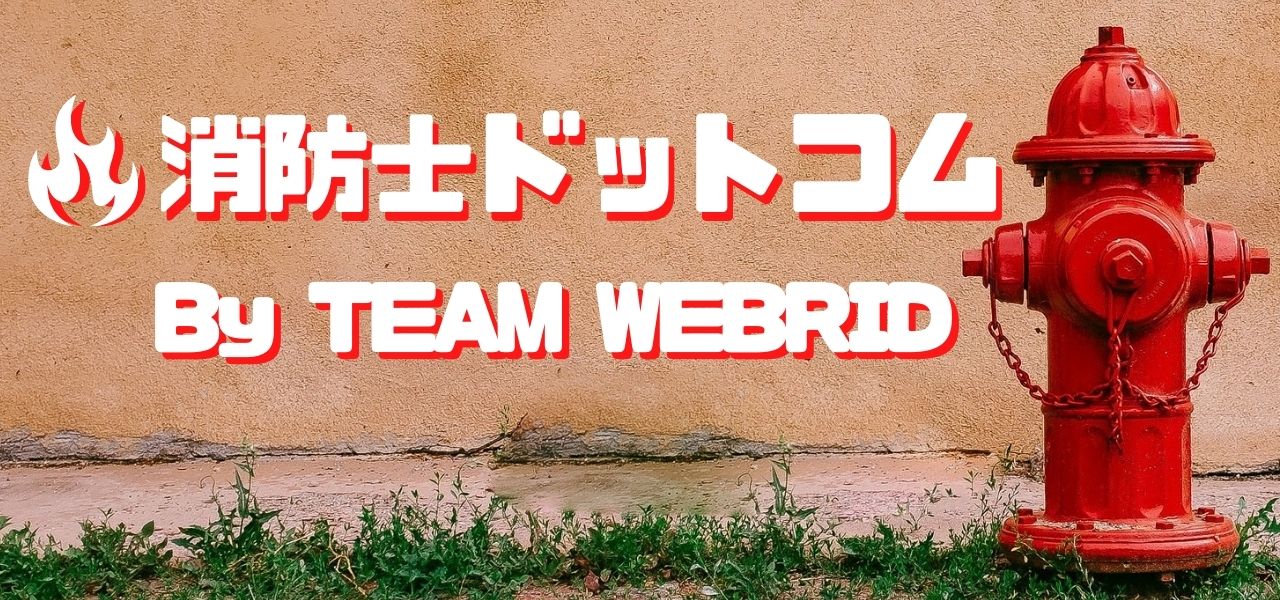

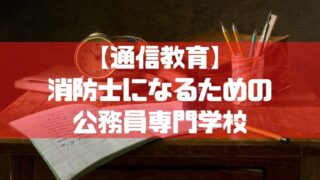








の違い-320x180.jpg)


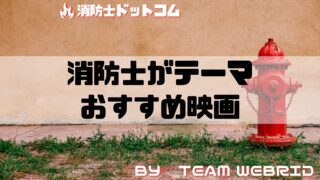














コメント