こんにちは、TEAM WEBRIDです。今回の記事のテーマは「投げる消火用具」について。
火災はいつ起こるかわかりません。もしものときに備えて、消火用具を持っていると安心ですが、消火器は重くて持ち運びに不便ですし、使い方は簡単ですが、難しそうなイメージが。そこで、今回は投げる消火用具についてご紹介します。
投げる消火用具とは、火災現場に投げ入れるだけで消火効果を発揮する画期的な製品です。簡単に使えて、効果も高いので、家庭や職場、車などに常備しておくと便利です。ただ、そんな投げる消火用具ですが、不適切な販売があったとネットニュースで話題になりました。今回はそのニュースについても、詳しく解説します。
今回の記事も、現役消防士や消防職員OBへの取材をもとに説明します。この記事を読むことで、「投げる消火用具」のことが理解できます。それではレポートします。
「投げる消火用具」とはなんだ?

投げる消火用具とは、その名の通り、火災現場に投げ入れるだけで消火効果を発揮する消火用具です。一般的には、消火剤を内蔵したプラスチックやガラスの球体や筒状の容器に入っています。火に触れると、容器が破裂して消火剤が散布され、火を消します。投げる消火用具のメリットは、以下の通りです。
投げる消火用具の種類と選び方 投げる消火用具には、主に以下の3種類があります。
投げる消火用具を選ぶときには、以下の点に注意してください。
不適切と指摘された「投げる消火用具」は何が不適切だったのか?

いざ本題です。「投げる消火用具」の何が不適切だったのか。それは消火能力を過大に表現していたとのこと。あたかも、一般的な住宅の居室内で発生する、当該居室の天井に炎の高さが届くまでの火災を、商品一つを投げるだけで、当該火災を消すことができる効果があるといった表示をしていました。
この内容が真実でない場合は、景品表示法違反(優良誤認)に当たります。が、現実として消費者庁により、消火能力について過大表現をしていた「投げる消火用具」を販売した5社に再発防止命令が出ました。その5社とは次のとおり。
いずれの会社も、2010年以降、天井に炎が届くほどの火災を商品一つで消火できると、ウェブサイトやパッケージ、動画広告などで表示していました。しかし、各社が提出した実験動画などには、合理的な根拠を示すものがありませんでした。実際の商品は次のようなものです。
ちなみに、消費者庁が根拠となる資料の提出を求めたところ、5社が提出したのは少量による火災を消す映像といったおそまつなものでした。そのため、天井に炎が届くほどの火災を商品一つで消火できるといった効果の裏付けとは認められないと消費者庁が判断したということです。情報元はこちらです。
令和4年5月25日消費者庁発出「投てき消火用具の販売事業者5社に対する景品表示法に基づく措置命令について」
✔️消防学校とは ✔️初任科の内容 ✔️初任科のカリキュラム ✔️初任科の準備(荷物編) ✔️初任科の準備(暗記編) ✔️初任科の準備(事前勉強編) ✔️初任科(勉強以外) ✔️初任科以外の入校
投げる消火用具は本当に使えないのか?
投げる消火用具は本当に使えないのかというと、そうでもありません。投げる消火用具の中にも、消火能力がしっかりと求められたものもあります。それがこちら、さきほども紹介したボネックスの投げ消すサット119エコ。
こちらは、前述のごとく、過大評価で表現修正は指示を受けたものの、消火能力は本物。なんと日本消防検定協会の性能鑑定を取得しています。
日本消防検定協会とは、総務省の所管団体で、消防機械器具等の試験及び検査を公正に行う機関として消防法に基づき設立されたもので、消火性能試験を実施し、消火能力の確認をしています。要は、消火性能が国のお墨付きってこと。ボネックスHPから商品説明を引用すると、
2004年4月、投げ消すサット119は投てき用特定初期拡大抑制機器として「日本消防検定協会の性能鑑定」に合格しました。 (消火弾タイプの消火機器として世界初)
日本消防検定協会 特定機器評価番号 特評第261号
全世界20か国以上の販売実績
小さく軽いので素早く持ち運べる
人体・環境にも無害、後始末も簡単
威圧感を与えない外観で身近に設置
ボネックスHPより
では、肝心の消火能力はどのくらいかというと、「投げ消すサット119エコ」を5本使用した時の消火能力が、普通火災の能力単位「1」とされています。消火能力の単位なんて言われると難しいですね、わかりやすく言うと、みなさんが一般的にみかける消火器は10型消火器と呼ばれています。こんなやつ。
このサイズの消火器の、普通火災の消火能力単位は「3」です。つまり、「投げ消すサット119エコ」15個合わせると、一般的な消火器の普通火災に対する消火能力と同等の性能ということです。
まとめ

今回は、投げる消火用具についてご紹介しました。投げる消火用具は、消火器と比べて、軽くて使いやすくて効果的な消火用具です。火災に備えて、自分のニーズに合った投げる消火用具を選んで、常備しておきましょう。
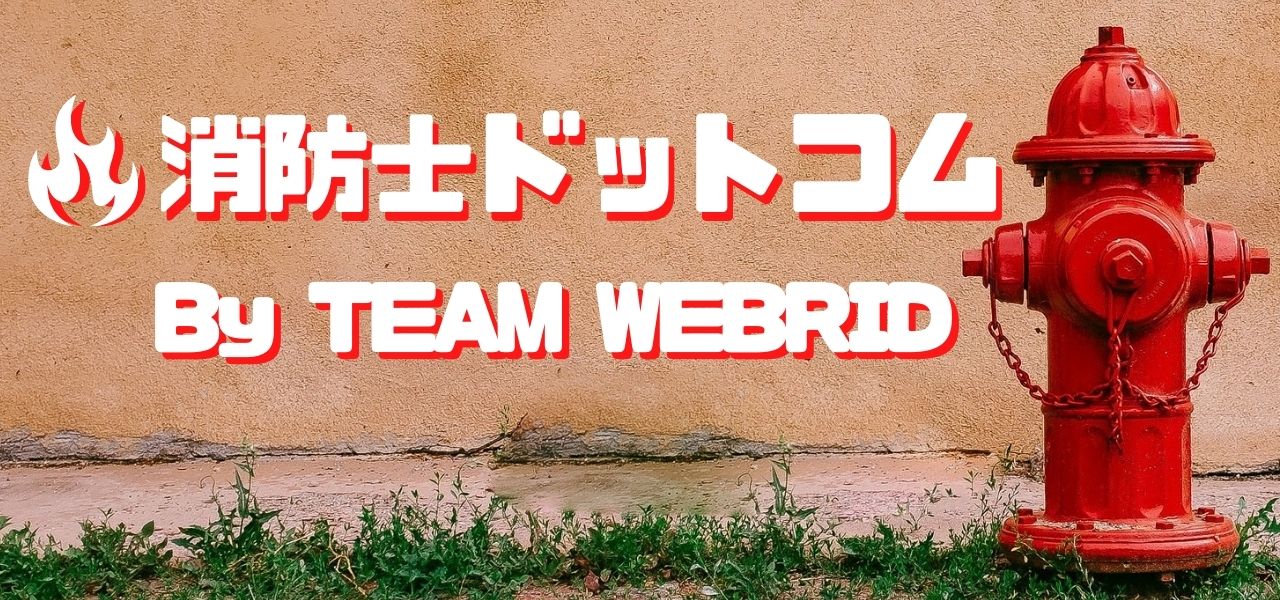

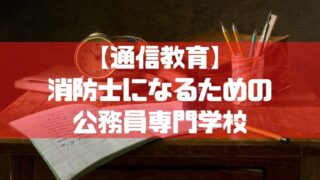








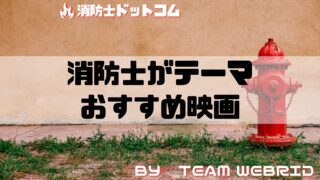








の違い-320x180.jpg)




は事実なのか?-120x68.jpg)
コメント
お世話様です。投げる消火用具についてご質問があります。
投げる消火用具は、消防法に定めのない物(メーカーが勝手に作った)とありますが、弊社商品「投げ消すサット119」は、日本消防検定協会の性能鑑定を取得し、消火能力単位を5本で1単位と認められた製品です。現状も型式適合検査を受け合格品としてNSマーク付与されて販売しております。これは明確に消防法の簡易消火用具として義務設置の1/2までは置き換えることのできる製品であり、総務省消防庁予防課より官報で各消防本部へ通達された物です。紹介されている他の4製品は不明ですが、弊社商品も同じとみているのでしょうか?ご確認ください。ご返事お待ちしております。
苅谷さま
ご指摘ありがとうございます。
こちらの記事は、令和4年5月25日付消費者庁発出「投てき消火用具の販売事業者5社に対する景品表示法に基づく措置命令について」
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms209_220525_01.pdf
に基づき、わかりやすい記事に仕上げたものとなっております。
表示内容の修正指示があっただけで、おっしゃるとおり、性能は認められていることが確認できました。
記事を修正させていただきます。
なお、効果的な「投げる消火用具」ということで御社の商品およびHPを記事内で紹介させていただいてもよろしいでしょうか?