こんにちは、TEAM WEBRIDです。今回は、消防士になったらすぐに派遣される消防学校での初任科の勉強内容について。初任科は、消防士としての基礎を身につけるため、新人消防士が必ず派遣される教育です。
全国には、都道府県が運営する消防学校や政令市が独自に運営する消防学校などがありますが、どこの消防学校に入ろうとも、必ず暗記させられる4つの項目があります。この4項目は、消防士として40年近く働くうえでも必須項目。
今回の記事も、現役消防士や消防職員OBの方への取材をもとにレポートします。ただでさえ、覚えることが多い初任教育です。この記事を読むことで、この4項目を暗記済みであれば、消防学校での勉強にゆとりが生まれます。
その分、他の勉強に割く時間が増やすことができ、好成績を狙うことができます。これから消防学校に入る人は、覚えておいて損はしません。
どこの消防学校(初任科)でも必ず暗記する必要があるもの①消防法第一条

消防法第一条は、どこの消防学校でも、必ず暗記させられます。どうしてか?それは、消防法第一条の内容が関係しています。これから消防士になろうとしている人に、
「消防士は何のために仕事をしているの?」
と聞いても、スラスラと正解を答えることができる人はまずいないでしょう。しかし、現役の消防士達はスラスラと答えることができます。なぜかというと、消防法第一条を覚えているから。その内容とは、次のとおり。
消防法第一条
この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。
消防法
ズバリ、「消防の目的」がうたわれています。消防に関することを定めている法律が消防法です。つまり、「消防の目的」というのは、「消防士の仕事の目的」ということ。覚えていて当然ですよね。自分の仕事の目的ですから。
目的を知らずに、仕事ができるわけがありません。でも、どうして仕事の目的が法律に書かれているのでしょうか?その答えは簡単、消防士が公務員だからです。公務員の仕事はすべて法律に従って成り立っています。
では、消防の仕事の目的とは具体的に何なのか?難しい言葉がならんでいるので具体的に確認してみます。箇条書きにしたらわかりやすくなります。消防士の仕事とは次のとおりです。
なるほど、確かに、消防士の仕事ですね。イメーどおり。自分の仕事の目的を明確にするため、消防法第一条を暗記することは、どこの消防学校でもマスト条件になっています。
どこの消防学校(初任科)でも必ず暗記する必要があるもの②消防組織法第一条

どこの消防学校でも、初任科で必ず暗記させられるものの二つ目は、消防組織法第一条です。消防組織法は、消防の組織について明文化された法律です。
消防の組織についてうたわれた法律の第一条には何が書かれているのでしょうか?
それは次のとおり。
消防組織法第一条
消防は、その施設及び人員を活用して、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災又は地震等の災害を防除し、及びこれらの災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行うことを任務とする。
消防組織法
このように、「消防の任務」がうたわれています。さきほどの消防法第一条では、「消防の目的」でしたよね、この目的を達成するためには、どのような任務をこなすことが必要なのかということがわかります。わかりやすいように、箇条書きに分けてみましょう。
確かに、これらの任務を適切にこなすことで、消防法第一条の
という目的は達成できそうですよね。目的を理解しているものの、達成するための方法を知らなければ意味がありません。そのため、目的だけでなく目的を達成するための任務内容を把握するために、消防組織法第一条の暗記は必須になっています。
どこの消防学校(初任科)でも必ず暗記する必要があるもの③消防法施行令別表第一

消防法に記載されている内容をもう少し詳しく具体的に説明したものとして、「消防法施行令」というものが存在します。法律だけでは説明しきれない部分を補ってくれる内容になっています。この消防法施行令の中では、世の中に存在する建物すべてを用途別に分けた表が存在します。具体的には、次のとおり。
| (一) | イ 劇場、映画館、演芸場又は観覧場 ロ 公会堂又は集会場 |
| (二) | イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの ロ 遊技場又はダンスホール ハ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第五項に規定する性風俗関連特殊営業を営む店舗(ニ並びに(一)項イ、(四)項、(五)項イ及び(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているものを除く。)その他これに類するものとして総務省令で定めるもの ニ カラオケボックスその他遊興のための設備又は物品を個室(これに類する施設を含む。)において客に利用させる役務を提供する業務を営む店舗で総務省令で定めるもの |
| (三) | イ 待合、料理店その他これらに類するもの ロ 飲食店 |
| (四) | 百貨店、マーケツトその他の物品販売業を営む店舗又は展示場 |
| (五) | イ 旅館、ホテル、宿泊所その他これらに類するもの ロ 寄宿舎、下宿又は共同住宅 |
| (六) | イ 次に掲げる防火対象物 (1) 次のいずれにも該当する病院(火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制を有するものとして総務省令で定めるものを除く。) (i) 診療科名中に特定診療科名(内科、整形外科、リハビリテーション科その他の総務省令で定める診療科名をいう。(2)(i)において同じ。)を有すること。 (ii) 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床又は同項第五号に規定する一般病床を有すること。 (2) 次のいずれにも該当する診療所 (i) 診療科名中に特定診療科名を有すること。 (ii) 四人以上の患者を入院させるための施設を有すること。 (3) 病院((1)に掲げるものを除く。)、患者を入院させるための施設を有する診療所((2)に掲げるものを除く。)又は入所施設を有する助産所 (4) 患者を入院させるための施設を有しない診療所又は入所施設を有しない助産所 ロ 次に掲げる防火対象物 (1) 老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第一項に規定する要介護状態区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な要介護者」という。)を主として入居させるものに限る。)、有料老人ホーム(避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第四項に規定する老人短期入所事業を行う施設、同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。)、同条第六項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの (2) 救護施設 (3) 乳児院 (4) 障害児入所施設 (5) 障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項に規定する障害者又は同条第二項に規定する障害児であつて、同条第四項に規定する障害支援区分が避難が困難な状態を示すものとして総務省令で定める区分に該当する者(以下「避難が困難な障害者等」という。)を主として入所させるものに限る。)又は同法第五条第八項に規定する短期入所若しくは同条第十七項に規定する共同生活援助を行う施設(避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。ハ(5)において「短期入所等施設」という。) ハ 次に掲げる防火対象物 (1) 老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(ロ(1)に掲げるものを除く。)、老人福祉法第五条の二第三項に規定する老人デイサービス事業を行う施設、同条第五項に規定する小規模多機能型居宅介護事業を行う施設(ロ(1)に掲げるものを除く。)その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの (2) 更生施設 (3) 助産施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童養護施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第七項に規定する一時預かり事業又は同条第九項に規定する家庭的保育事業を行う施設その他これらに類するものとして総務省令で定めるもの (4) 児童発達支援センター、児童心理治療施設又は児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援若しくは同条第四項に規定する放課後等デイサービスを行う施設(児童発達支援センターを除く。) (5) 身体障害者福祉センター、障害者支援施設(ロ(5)に掲げるものを除く。)、地域活動支援センター、福祉ホーム又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第七項に規定する生活介護、同条第八項に規定する短期入所、同条第十二項に規定する自立訓練、同条第十三項に規定する就労移行支援、同条第十四項に規定する就労継続支援若しくは同条第十五項に規定する共同生活援助を行う施設(短期入所等施設を除く。) ニ 幼稚園又は特別支援学校 |
| (七) | 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学、専修学校、各種学校その他これらに類するもの |
| (八) | 図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの |
| (九) | イ 公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場その他これらに類するもの ロ イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 |
| (十) | 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場(旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。) |
| (十一) | 神社、寺院、教会その他これらに類するもの |
| (十二) | イ 工場又は作業場 ロ 映画スタジオ又はテレビスタジオ |
| (十三) | イ 自動車車庫又は駐車場 ロ 飛行機又は回転翼航空機の格納庫 |
| (十四) | 倉庫 |
| (十五) | 前各項に該当しない事業場 |
| (十六) | イ 複合用途防火対象物のうち、その一部が(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供されているもの ロ イに掲げる複合用途防火対象物以外の複合用途防火対象物 |
| (十六の二) | 地下街 |
| (十六の三) | 建築物の地階((十六の二)項に掲げるものの各階を除く。)で連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたもの((一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。) |
| (十七) | 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品として認定された建造物 |
| (十八) | 延長五十メートル以上のアーケード |
| (十九) | 市町村長の指定する山林 |
| (二十) | 総務省令で定める舟車 |
難しい言葉が続きますね。ところどころ、何を言っているのかわからない。しかし、この場では、深いことは考えなくても大丈夫。消防学校でも、初任科だけでは内容すべてを理解できません。
ただ、唯一はっきりしていることは、この表は丸暗記する必要があるということ。座学でのテスト、消防学校では「効果測定」と言いますが、効果測定に必ず出ます。消防士にとっては基本中の基本。
こんな表を、消防学校に入って覚えることが山ほどある中で覚えるのは大変。だから採用前に覚えておくと相当楽になります。ちなみに、なぜこれらの暗号みたいなものを覚える必要があるのかというと、予防業務には欠かせない知識だからです。というのも、屋内消火栓やスプリンクラー設備といった消防設備は、建物の
などにより、設置が必要な消防設備が決定されます。その際、例えば
といった具合に、上の表から判断するわけです。消防士を目指している人の中には、
「いやいや、僕はレスキュー隊になるから予防業務はしない」
「いえいえ、私は救急救命士になるから予防業務はしない」
ということを考えている人も多いはず。しかし、予防業務に従事することがないなんて保証はどこにもありません。消防本部の規模によっては、消防隊と予防業務を兼任しています。兼務制ではない消防本部に採用されていても、部署異動により予防係になる可能性は全員持っています。
あえて、一番予防係になる可能性が低いとすれば、救急救命士の資格を持った状態で、救急隊員専任性の消防本部に採用された場合ぐらいでしょうか。でも、もしかしたら腰を痛めてしまって現場活動が難しくなり、予防業務専任になるかもしれません。ということで、消防学校の初任科では、消防法施行令別表第一の暗記テストがマスト条件になっています。
✔️消防学校とは ✔️初任科の内容 ✔️初任科のカリキュラム ✔️初任科の準備(荷物編) ✔️初任科の準備(暗記編) ✔️初任科の準備(事前勉強編) ✔️初任科(勉強以外) ✔️初任科以外の入校
どこの消防学校(初任科)でも必ず暗記する必要があるもの④火災の定義

火災にも、定義があります。というか、何にでも定義がないと判断できませんからね。その定義とは次のとおり。
火災とは、人の意図に反して発生し若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は、人の意図に反して発生し若しくは拡大した爆発現象をいう
難しくややこしいですね。分解して理解しましょう。
かつ
または
どうしてこのような定義が必要なのか。具体例を挙げるとわかりやすくなります。消防の仕事として判断に困ることを、この定義が助けてくれます。例えば、町内会で公園の落ち葉集めをして焚火をし、焼き芋を楽しんでいたとします。意地悪なおじさんが、その楽しそうな雰囲気を妬み(ねたみ)、消防署へ
「公園で火事だ、炎があがっている!」
と通報したとします。通報があれば消防車は出動します。消防車が現場到着して状況を確認します。確かに公園で炎があがっているものの、消火活動を行うことはありません。通報を行った意地悪おじさんは消防隊を怒鳴ります。
「お前ら火事を目の前にして何やっているんだ、早く消せ!」
ここで、火災の定義の出番ですね。消防隊は、意地悪おじさんに説明します。内容の要点はこれ。
”人の意図に反しておらず、意図的に燃やしているので火災とはいえない”
つまり、火災の定義に合わないわけです。ただ、これだけだとあまりにも杓子定規なやりとりになるので、状況を確認したうえでの説明も付け加えます。
これらの理由で、消防隊による消火の必要性はないときっぱり伝えます。火災であれば火災報告書の作成が必要になります。火災であれば、火災保険の対象にもなります。つまり、火災かどうか、火災じゃないのかどうかということは、とても大きな判断です。この事例の場合は、火災報告書の作成も不要です。出動記録を残すのみです。
消防学校(初任科)で必ず暗記する必要があるもの4選のまとめ

どこの消防学校でも必ず暗記をして効果測定(テスト)を受ける必要がある4つの項目について説明しました。まとめると次のとおり。
消防学校に入る前に暗記しておくと、消防学校での生活がぐっと楽になることも納得の暗記ボリュームです。消防人生で一生使う知識です、がんばってインプットしてください。
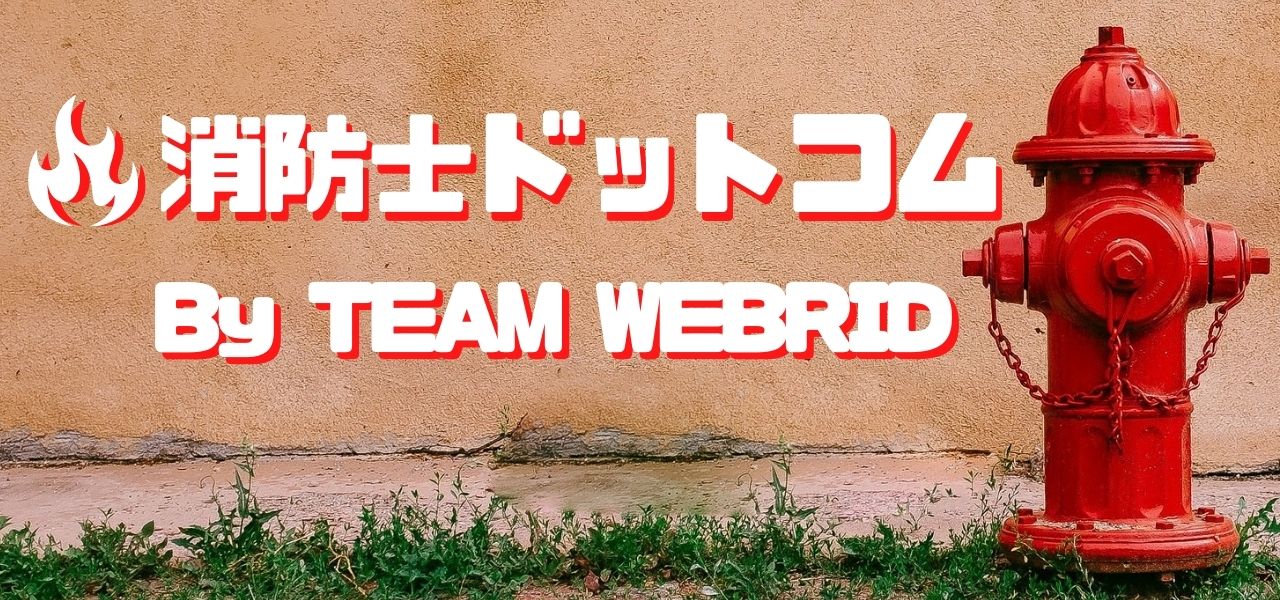

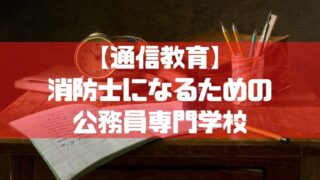
















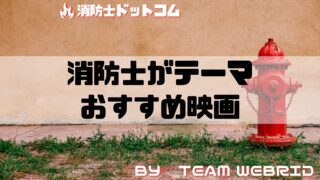
の違い-320x180.jpg)


でも必ず暗記する必要があるもの4選.png)
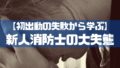

コメント