この記事では、消防士の休みをテーマとして解説します。24時間の交代勤務を行う消防士が、24時間起きたまま働きっぱなしなのでしょうか?実は、仮眠時間や休憩時間がきっちり決まっています。この記事では、休憩時間の解釈だけでなく、消防士の交代勤務についても説明します。この記事を読むことで、消防士の勤務中の休みや、勤務体制の仕組みがしっかりと理解できることでしょう。それではレポートします。
消防士の勤務体制:消防士の勤務の種類

消防士の勤務には、大きく分けて次の2種類の勤務があります。
消防士の勤務体制:毎日勤務

毎日勤務というのは、普通のサラリーマンと同じで、月曜日から金曜日までが勤務日となっており、土曜日、日曜日が週休日となっています。一般的なサラリーマンと同じなので、カレンダーとおりの勤務です。
勤務時間は、午前8時30分から、午後5時15分までとなっています。その間、午後0時から午後1時までは、休憩時間です。国民の祝日にあたる休日ももちろん休みになります。1点だけ、普通のサラリーマンと違うところがあります。それは、お盆休みがないことです。
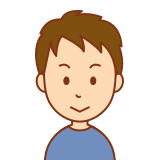
え?他はカレンダーとおり普通のサラリーマンと同じように休みなのに、なんでお盆は休みじゃないの?
と、みなさん、考えると思いますが、カレンダーをよく見てみてください。8月の旗日は「山の日」だけで、13日、14日、15日は平日扱いです。そうです、世間の方が、国民の祝日を定める法律で定まっていない日に休みをもらっているのです。不思議ですね。あとは、正月休みが短い。12月の29日から、1月の3日までが正月休みになります。4日から仕事が始まるって聞くと、世間よりかなり早い仕事始めだと思われます。
カレンダーの旗日は1月1日だけですが、これにあっては、各市町村の条例で、12月29日、30日、31日、1月2日、1月3日を休日と定めることで、正月休みとしているようです。
消防士の勤務体制:交代勤務

消防本部によって異なり、2交代制、3交代制の本部があります。天下の東京消防庁は3交代制です。ここでは、2交代制の交代勤務について解説します。
3交代制に勤務体制についても詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
勤務時間は?
午前8時30分から翌日の午前8時30分までが勤務時間です。その中で、休憩時間を除くと実際に働く時間は午前8時30分から午後0時までの3時間30分。午後1時から午後5時15分までの4時間15分。午後6時45分から午後10時までの、3時間15分。午後10時から翌朝の午前6時までの間で夜間通信勤務を2時間。午前6時から午前8時30分までの2時間30分。
合計15時間30分。
これは、日勤者が、午前8時30分から午後0時までの3時間30分と、午後1時から午後5時15分までの4時間15分働くことで、1日あたり7時間45分働く事になりますが、ちょうどその2倍(2日分)になっています。
休憩時間は?
午後0時から午後1時までの1時間。午後5時15分から午後6時45分までの1時間30分。午後10時から翌朝6時までの中で、夜間通信勤務の2時間を除いた、6時間。合計、8時間30分の休憩時間となっています。
仮眠ってできるの?
仮眠は、休憩時間内なら可能となっています。だいたいどこの消防本部も、交代勤務者用のベットや畳など、寝室の用途に使う施設があります。特に、深夜時間帯も出動頻度の高い救急隊員などは、夜中の救急出動に備えて、午後5時15分から午後6時45分までの休憩時間などに仮眠をとることが日常化しています。もちろん、その間に救急出動がかかれば、即座に出動します。
夜間の休憩時間は、午後10時から翌朝の午前6時までの8時間と長いように思えますが、その中で2時間の夜間通信勤務に携わるため、実際には6時間の仮眠になります。ただ、連続で6時間の間、出動等がなければぐっすり眠れるというわけでもありません。一般的に多いのは、午後10時から翌朝の午前6時までを、2時間ごとで区切り、夜間通信勤務を行います。
といった具合です。例えば、午前2時から午前4時の夜間通信勤務の当番になった場合、午後22時から午前2時まで仮眠、午前4時から午前6時までが仮眠ということになります。
休みはどうなっているの?

2交替制の場合、多くの本部が、2交替を行う2つのグループを1係、2係と分けています。
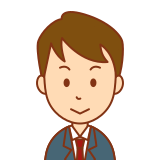
今日はお休みのため、消防車は出動できません。
というわけにはいかないのが消防署です。24時間、365日、災害対応可能な状態でいる必要があります。そのため、2つのグループで、24時間交替で勤務を行っているというわけです。ある月に注目したとすれば、奇数日は1係、偶数日は2係が勤務します。
例えば、自分が1係になったと想像してください。今月は奇数日が勤務日だとします。1日の午前8時30分から仕事を始めます。そして2日の午前8時30分に仕事を終えます。2日の午前8時30分から3日の午前8時30分までは非番日となり、つまりはお休みということです。家に帰り、寝るもよし、遊びに行くもよしの日となります。
次の仕事は、3日の午前8時30分からです。4日の午前8時30分まで仕事をします。文章だとわかりにくいので、リスト化してみると
- 1日 勤務
- 2日 休み(非番日)
- 3日 勤務
- 4日 休み(非番日)
- 5日 勤務
- 6日 休み(非番日)
- 7日 勤務
- 8日 休み(非番日)
- ・・・以下同じ・・・
と続きます。
1日おきに休みがあるように見えますが、実際は災害対応などで仮眠が取れない日などもあり、24時間勤務の休息をとる日となります。わかりにくいので、1日の勤務日と、2日のお休み(非番日)をセットで考えるとイメージがしやすいかと思います。
前述したように、日勤者は、1日に7時間45分働きます。2日にも7時間45分働きます。1日と2日で15時間30分働くことになります。交代勤務者は、1回仕事に行くと、15時間30分働くことはすでに述べたとおりです。
つまり、2日間という枠で見ると、日勤者も交代勤務者も同じ時間(15時間30分)を働いているということになります。ここでおかしいと思いませんか?
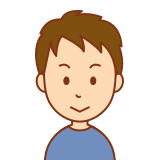
あれれ?
交代勤務者って、1日ごとに休みがあるように見えるけど、実際には1回仕事に行くと、2日分働いたことになるなら、ずーっと奇数日に仕事に行ってたら、日勤勤務の人が、土日もなくずーっと働いているのと同じになるんじゃないの?
そうです。その通りです。では、休みをどのように考えるかを説明します。日勤者は、月曜日から金曜日まで、5日働き、土曜日と日曜日の2日休みます。7日のうち、5日働き、2日休み。この考えを、2日セットで働いている交代勤務者にあてるのは無理ですよね。そこで工夫をします。
その工夫とは、4週間単位で、勤務日と休みの日を考えることです。日勤者の場合、4週間のうち、勤務日は20日(5日×4週間)あり、休みの日は8日(2日×4週間)あります。この考えを、交代勤務者にあてがいます。4週間は28日あります。休みなく働いたとすると、14日が勤務日で、14日が非番日です。
このままだと、先ほどから説明しているように、休みがありません。日勤者が28日休みなく働いているのと同じ状況です。そこで、勤務日のうち、4つの勤務日を休みにします。
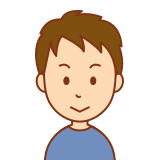
え?ちょっと待って、日勤者は4週間で8日休みなのに、交代勤務者はどうして4日だけ?
答えは簡単、交代勤務者は、1回仕事に行くことで、毎日勤務者の2日分働くと説明してきましたよね。ということは、交代勤務者が1回仕事を休むということは、毎日勤務者にとっての2日分を休むということになります。
つまり、交代勤務者は4週間の中では、10回仕事(日勤者の2日分×10回=日勤者の20日分働く)に行き、4回仕事(日勤者の2日分×4回=日勤者の8日分休む)を休みます。今さらですが、交代勤務者の場合、仕事の日のことを当務日といいます。仕事が終わる日のことを非番日といいます。
また、仕事に行かなくてもよい勤務日のことを週休日といいます。仕事に行かなくてもよい日の次の日(別のグループが働く日、もしも仕事に行ってた場合は、仕事が終わる日)のことを週休非番日といいます。わかりやすく順を追ってリスト化してみます。あなたが奇数日が勤務日の1係になったとイメージしてください。すると
- 1日 当務日
- 2日 非番日
- 3日 当務日
- 4日 非番日
- 5日 当務日
- 6日 非番日
- 7日 当務日
- 8日 非番日
- 9日 当務日
- 10日 非番日
- 11日 当務日
- 12日 非番日
- 13日 当務日
- 14日 非番日
- 15日 当務日
- 16日 非番日
- 17日 当務日
- 18日 非番日
- 19日 当務日
- 20日 非番日
- 21日 当務日
- 22日 非番日
- 23日 当務日
- 24日 非番日
- 25日 当務日
- 26日 非番日
- 27日 当務日
- 28日 非番日
のようになります。このままでは、休みがなく、日勤者が28日間毎日働いているのと同じことになってしまうので4回週休日が入ります。週休日の翌日は、偶数日であり、2係のグループの人たちが仕事をする日であるため、1係のあなたは働く必要はありません。前述の週休非番日というものになります。リスト化すると、
- 1日 当務日
- 2日 非番日
- 3日 週休日
- 4日 週休非番日
- 5日 当務日
- 6日 非番日
- 7日 当務日
- 8日 非番日
- 9日 当務日
- 10日 非番日
- 11日週休日
- 12日 週休非番日
- 13日 当務日
- 14日 非番日
- 15日 当務日
- 16日 非番日
- 17日 週休日
- 18日 週休非番日
- 19日 当務日
- 20日 非番日
- 21日 当務日
- 22日 非番日
- 23日 週休日
- 24日 週休非番日
- 25日 当務日
- 26日 非番日
- 27日 当務日
- 28日 非番日
このような4週間のライフサイクルとなります。ちなみに、赤い文字になっているところは、仕事に行かなくてよい日です。ぱっと見ると、4週間に、3連休が4回もあるように見えますよね。3連休といっても、1日目の非番日は、前日の仕事の内容次第では、非常に睡眠不足な状態であることは前述のとおりです。
ただ、そのあたりの小さな事情があるにせよ、4週間に3連休が4回あるというこのあたりが、消防士は休みが多いと世間で言われる理由だと思われます。実際は、4週間単位での仕事の時間も休みの時間も、日勤者と全く同じ時間になっています。このからくりの理由は、交代勤務者は、まとめて働く分、休みがまとめてくるため、休みが多く見えるのです。
もう一度言います、このように言われる理由は、交代勤務者は、まとめて働く分、休みがまとめてくるため、休みが多く見えるのです。
✔️消防学校とは ✔️初任科の内容 ✔️初任科のカリキュラム ✔️初任科の準備(荷物編) ✔️初任科の準備(暗記編) ✔️初任科の準備(事前勉強編) ✔️初任科(勉強以外) ✔️初任科以外の入校
休みたい日を希望して休めるの?

交代勤務の消防士は、最低確保人員という、1日に消防署に勤務が必要な人数が決まっています。その理由は、同時出動が必要な消防車の数が決まっており、1台の消防車に乗る人数も決まっているためです。
つまり、勤務を予定していた日に急遽、体調不良などで仕事に行けないとなった場合、本当は休みの予定だった人が、体調不良で休む人の代わりに勤務をすることになります。代わりに仕事に来た人にとっては、休みがなくなるという損をするわけではなく、週休日を変更して休みだった日を当務日にしたり、もしくは週休日に勤務した時間を時間外勤務手当の支給によりまかなうといった方法をとります。
このように、急に休みをとると、ほかの人に迷惑をかけるということはわかりましたが、事前に休みを取りたい希望日がある場合はどうするのでしょうか。4週間ごとの勤務表ができあがる前に、休みを取ることが必要な日がわかっている場合は、その休みが必要な日に週休日を入れてもらうことで、希望の日に休みを取ることができます。
では、4週間ごとの勤務表ができあがった後に、休みをとることが必要になった場合はどうでしょうか。それは、同じ係の人に交渉して、週休日を交換してもらう方法や、最低確保人員が足りている日であれば有給休暇を取得するといった方法があります。就職して、ある程度年数がたてば、融通が利きやすくなります。人間関係が形成できれば、休みがとりやすくなるのは、消防に限らずどこの職場でも同じようです。
消防士の休み|勤務時間と休憩時間の制度と仕組みのまとめ

消防士の勤務体制、特に「休み」について詳しく解説してみましたが、理解できたでしょうか。交代勤務ってややこしいですね。休みが多い多いとうわさされる消防士も、実際は4週間単位で考えると普通のサラリーマンと同じ時間しか働いていませんでした。
今後も、新しい情報が入り次第、レポートを更新していきます。
この記事を読まれた方で、さらに詳しく知りたいことがあれば追跡調査しますので、コメントか問い合わせフォーム、またはTwitterにてご質問ください。
また、消防関係者の方で、うちの本部ではこうなってるよ、それは違うんじゃない?などのご意見をいただける際も、コメントか問い合わせフォーム、またはTwitterにてご連絡いただけると助かります。
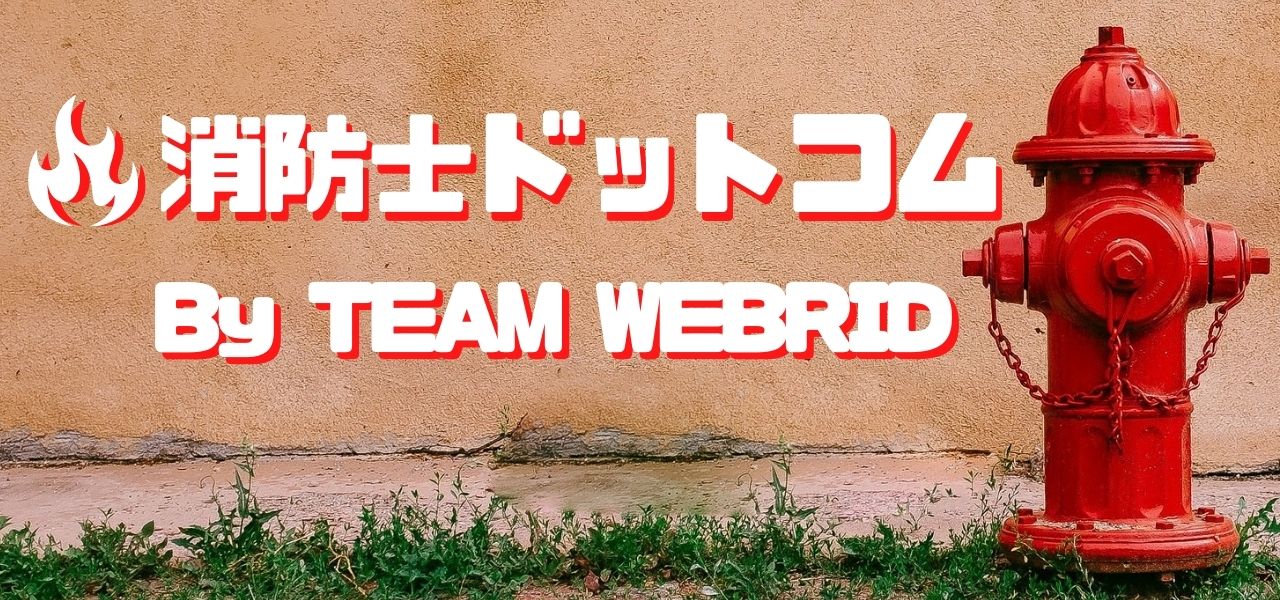

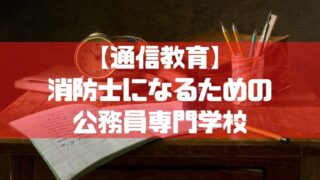












の違い-320x180.jpg)


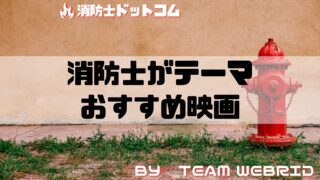








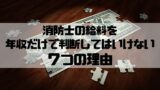



コメント