消防士採用試験についてこの記事を読んだらわかること

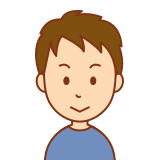
消防士採用試験を受けようと思っています!
体力試験について、どんなものなのか教えてください。
この記事では、消防士採用試験で実施される体力試験についてレポートします。やはり、消防士の仕事の内容を考えると、相当な体力、筋力が必要なことは言うまでもなく、消防士の採用試験で行われる体力試験は、受験生にとって不安で一杯ですよね。そんな受験生の不安を解消すべく、受験生の立場になって不安が解消されることに重点を置いた記事となっています。
今回の記事も、現役消防士の方や消防職員OBの方々からの調査結果をもとにレポートしたいと思います。この記事を最後まで読むことで、きっと、あなたの採用試験への不安が解消できます。
\消防士採用試験を知りたい方はこちらの記事/
消防士採用試験の体力試験は足切りで落ちる?体力試験の種目(女性も含む)について解説

消防士は、各自治体によって運営されていますので、全国的に統一された試験はありません。消防本部の採用案内を見ると、体力試験の項目を記載している本部が多く見受けられます。東京消防庁も採用専用のホームページを立ち上げています。志望する本部が決まっている人は、ホームページなどで体力試験の内容を確認してください。ここでは、一般的な次の種目について紹介します。
消防士の体力試験:腕立て伏せ
手を肩幅に開き、だれもが知っている一般的な腕立て伏せを行います。「ピッ」という笛の合図とともに開始します。受験生によって、ゆっくり行うタイプや素早く行うタイプなど、腕立て伏せのやり方が違うと不公平になるので、メトロノームなどのリズム器を使って一定のリズムで統一して行います。
言い換えると、この一定のリズムに遅れてしまうと、そこで測定終了になります。また、人によっては、体を下げた時の高さが異なることで、不公平になります。そこで、体を下げた時の高さを、例えば、
といった基準を設けています。一般的には10センチから15センチが多いようです。試験自体は、一定の回数に到達すればストップ、または一定時間内に何回できるかをもって測定結果になります。一般的には2分の間に50回から60回を上限としている本部が多いようです。2分ということは120秒ですね、1秒で下げて、1秒で上げる、つまり2秒に1回腕立て伏せを行った場合、120秒で60回の腕立て伏せを行うことになります。そう考えると、イメージがしやすいかと思います。
採用試験に向けたトレーニングの際にも、正しい姿勢と、正しいリズムで行ってください。浅い位置での素早い腕立て伏せではなく、しっかり伸ばし、しっかり曲げる腕立て伏せができるようになれば、採用試験の腕立て伏せにおいて、アドバンテージが取れるということになります。女性についても、腕立て伏せは男性と同様の内容で実施する消防本部がほとんどです。女性に合わせた腕立て伏せというものがそもそも存在しないということがその理由です。
消防士の体力試験:腹筋
誰もが知っている、いわゆる腹筋を競うものです。一定時間内の回数を競ったり、一定回数に達するまでの時間を競ったり、本部によって違いがあるようです。腹筋もやり方によっては、回数に対して疲労の違いが出ますので、一定の基準が設けられています。
まず、床と水平(仰向け)になったときは、背中が床面に接することが条件になります。また、腹筋をするときの腕は、頭の後ろに組む姿勢が一般的です。そのため、体を起こしたときは両腕の肘が、膝に接することが条件になります。腹筋を行うときの姿勢は、フラットな床の上にマットを置き、受験生同士で足を押さえあうパターンや、または、一般的な腹筋台に足を固定して行うパターンがあります。
トレーニングの際には、中途半端な動きの腹筋は控え、前述のとおり、上半身の振れ幅が最大限になるように心がけましょう。本番同様の練習をすることが重要です。女性についても、男性と同様の試験内容となっています。
消防士の体力試験:懸垂
懸垂と聞くと、鉄棒にぶら下がる姿をイメージすると思いますが、ましくそれです。回数を測ります。ただ、懸垂方法によっては、正しく筋力が測れないので一定のルールがあります。まず、手は順手で、肩幅より少し広めに開いて、鉄棒にぶら下がります。ぶら下がって静止した状態から、試験官の合図によりスタートします。
リズムを指定しないパターンや、3秒に1回のリズムで合図が鳴り、体を持ち上げるパターンがあります。体を上にあげたときは、あごが鉄棒を超える、または、あごを鉄棒にタッチすることが必要です。体をおろしたときは、肘がまっすぐ伸びることを条件としています。
肘の伸ばし方が中途半端であったり、あごがしっかり鉄棒を超えていないと回数をカウントしてもらえないので注意が必要です。肘を伸ばしきるときと、伸ばしきらずにまた体を持ち上げるときでは、使う筋肉が違ってきます。普段のトレーニングでも、肘を伸ばしきることに意識をしてください。
女性の場合、筋力のつき方的に、男性の懸垂と同様のルールにしてしまうと受験生全員が0回という結果になりかねません。つまり、差がつかないということです。差がつかないのであれば試験を実施する意味がありません。そこで女性の場合は、一般的な懸垂ではなく、ぶら下がり懸垂を行い、ぶら下がる時間を測定するといった試験を実施している消防本部があります。
消防士の体力試験:土嚢運び
みなさん、土嚢(どのう)ってわかりますか?簡単に言うと、砂を詰めた袋のことです。中に入れる砂の量にもよりますが、一般的には20キログラム程の重さになります。よく台風が迫って来るときに、テレビで見かける白い袋です。この土嚢を担いで、一定の距離を走る時間を競います。試験によっては、楕円形のコースをまわったり、直線の距離を往復します。
走る体力というよりは、重いものを持って走れるかの筋力を競うものと考えてください。楕円形のコースを走るタイプの試験では、重いものを持って速く走ろうとすることに慣れていないために、土嚢袋の重さと遠心力でカーブの際に転倒する受験生が多くいます。体幹を鍛えておくことが重要です。
受験生の体重によって土嚢袋の重さを変えてくれるようなものではありませんので、体格差が影響する種目です。体幹と足腰をしっかり鍛えておきましょう。女性の場合は、男性と同様の試験を行うか、または土嚢の重さを少し軽くして行う場合があります。
消防士の体力試験:時間往復走
体力テストで行う種目です。一定の距離を走り、リズムに合わせて走ります。みなさん、義務教育の中でしっかりやってきていると思いますので、大きな違いがないため割愛します。脚力を測定するだけではなく、体力や持久力を主に測定する種目です。普段から、長距離を走ることで、肺の機能を高めておきましょう。
この種目については、男女の差はありません。採点については、文科省の新体力テスト実施要項に準じている消防本部が多いため、男女の採点に差を設けていない消防本部がほとんどです。
\遠保での受験はこちらがお得/
消防士の体力試験:垂直飛び
これも体力テストで行う種目です。腕を耳につけて上に伸ばし、指で黒板のような板を上にずらします。あとは、上に向かってまっすぐジャンプします。また、実施本部によっては、腰にベルトのようなものをまき、床に置いたマットに、ベルトから伸びた紐をセットし、ジャンプしたときの飛距離を測定できる器具を使う本部もあります。
スクワットなどで、脚力を高めておくことが重要です。女性は男性に比べて脚力が弱い分、体重も軽いので男性と同様の試験内容で行うことが一般的です。
消防士の体力試験:立ち幅跳び
これも体力テストで行う種目と同様です。学校では砂場などで行いましたが、消防の採用試験の体力テストは体育館で行われることが一般的です。ジャンプの後、尻もちをつかずに静止して、スタート線からジャンプ後のかかと位置までの距離を測定します。
垂直飛びと同様に、スクワットなどで脚力を高めておきましょう。女性の場合も、垂直飛びと同様の考え方で男性と同じ試験内容となっています。
消防士の体力試験:シャトルラン
反復横跳びと、時間往復走の中間のような種目です。一定の距離(だいたい5mから8mが一般的)にひかれた境界線の間を決められた時間内に何往復できるかを測定します。足が完全に境界線を越えるか、境界線のさらに奥にひいた線にタッチするかを判定基準とします。短距離の速さと、ターンの速さで差がつきます。
体力より、筋力が影響します。上記の垂直飛びや立幅と同様に脚力が必要です、下半身のトレーニングが影響します。女性も男性と同様の内容で実施します。消防本部によっては、採点基準の時点で男性と女性の差を設けている場合があるようです。
消防士の体力試験:握力
これも体力テストで行うものと同様です。腕を体の横につけて測定器具を握ります。握力テストをやったことがない人はいないと思うので、詳細は割愛します。握力は、懸垂に必要な筋力です。言い換えると、懸垂をしっかりトレーニングすることで、必然的に握力はついてくるので、特段のトレーニングは必要ありません、懸垂を頑張りましょう。
女性の場合、どうしても男性と差が出てしまうのでほとんどの消防本部で採点基準に差を設けているようです。
消防士採用試験の体力試験時の服装はどうしたらいいのか?

体力テストのときは、みんなスポーツウエアです。部活で使っていたような服から、スポーツジムで見かけるような服、中には高校の体操服を着ている受験生もいます。やはり、消防士を目指すだけあって色々なスポーツ界でそれなりの成績を残している受験生も多く、インターハイや国体、インカレなどの記念シャツでアピールする受験生もいます。
ただ、あくまでも公務員試験ですので、部活の成績が体力試験の結果に影響することはなく、体力試験での採点は体力試験の結果のみとなります。注意することは、スポーツウェアのまま会場に行くのか、そうでないのかということです。これは、受験する消防本部の試験日程によります。本部によって、一次試験の筆記試験、小論文、体力試験等を1日で実施するところと、2日に分けるところがあります。
2日に分ける場合は、体力試験の会場までスポーツウェアで向かいます。1日ですべての試験を終わらせる場合はリクルートスーツで向かい、途中で着替えます。このあたりは、受験する消防本部の受験案内をしっかり確認してください。着替える場所についての記載を見落とさないようにしましょう。
\筆記試験についての詳細はこちら/
一般的な持ち物は次のようなものです。
消防士採用試験の体力試験で足切りにより落ちるパターン


自分は筋力・体力がないから、消防士は無理だ!受からない!
というのは大きな間違い。なぜなら、筋力も体力もトレーニングで身につくから。具体的に言うと、採用後に派遣される消防学校で6か月間、消防士としての基礎を身につけます。
\消防学校に関する情報はこちら/
つまり、採用試験での体力試験で何を判断しているかというと、

この受験生は、いくらトレーニングをしても、筋力、体力がついてくる見込みがないな。
ということ。例えば、懸垂が3,4回できれば、あとはトレーニングで回数が増えるだろうということは誰でもわかりますよね。でも、懸垂が1回もできない人が6か月の訓練だけで基礎が身につくとは考えにくい。一言でいうと、受験生の中で、受験生の中での平均より低い結果だとしても、足切りはされません。
逆に、最低限(懸垂が1回もできない、飛べない、走れない、重い物を運べない)にも達していなければ足切りされてしまいます。女性の場合も、男性と同様の考え方です。伸びる要素があるかどうかが大事な判断基準となっています。
✔️消防学校とは ✔️初任科の内容 ✔️初任科のカリキュラム ✔️初任科の準備(荷物編) ✔️初任科の準備(暗記編) ✔️初任科の準備(事前勉強編) ✔️初任科(勉強以外) ✔️初任科以外の入校
消防士採用試験の体力試験について採点基準と点数

SNSやインターネットの書き込みでは、

体力試験がダメだったから消防士の採用試験に落ちた!
というような意見がありますが、大きな間違いです。99%学科試験の力不足です。上記のとおり、体力試験は、トレーニングで伸びる可能性がない受験生を落とす、足切りを目的としています。消防士の採用試験を受けようとする人は、それなりに部活等を頑張ってきた人が多いはずです。部活等を五体満足で行えてきたような人は、体力試験と筆記試験にかける努力は、1対9から0対10ぐらいで十分です。
\遠方での受験はこちらがお得/
消防士採用試験の体力試験当日の日程

体力試験当日の日程は、受ける本部によって異なります。学科試験と体力試験を同一日で行う場合は、午前中に体力試験を実施し、午後から学科試験を行います。学科試験と体力試験を2日に分けて行う場合は、午前から体力試験を実施し、終わり次第解散になります。
本部の規模や、受験生の数によっても違いが出ますので、自分が受ける消防本部の受験案内をしっかりと確認し、間違えないようにしましょう。他の受験生と違った目立つ行動をとってしまうと、受験案内さえまともに読めない人だという悪印象を与えてしまい、チェックが入ることになります。
消防士の採用試験|体力試験まとめ|合格基準と足切りのまとめ

消防士採用試験の体力試験について、種目の内容を重点的にお話ししましたが、どのような印象を受けたでしょうか。消防士になる人は、消防士になる前からみんなが体力、筋力ともスーパーマンなわけではないということが伝わったでしょうか。もちろん、良い記録を出して、他の受験生よりアドバンテージを持つことも良いことです。
ただ、良い記録が出ないから受からない、というわけではありません。採用試験のときは、懸垂が2回しかできなかった、という消防士も現実にいます。また、初めて挑戦した消防士採用試験で合格する人というのは少なく、消防浪人を乗り越えて合格する人の方が多い年もあります。
\消防浪人について詳しく知りたい方はこちらの記事/
体力試験は、最低限の運動ができるかできないかの足切りを行っているものだということを理解してください。体力試験だけでなく、筆記試験を含む消防士採用試験全般について情報を探している方は次の記事を読んでみてください、あなたの力にはるはずです。
\消防士採用試験の全般について詳しく知りたい方はこちらの記事/
今後も、新しい情報が入り次第、レポートを更新していきます。
この記事を読まれた方で、さらに詳しく知りたいことがあれば追跡調査しますので、コメントか問い合わせフォーム、またはTwitterにてご質問ください。
また、消防関係者の方で、うちの本部ではこうなってるよ、それは違うんじゃない?などのご意見をいただける際も、コメントか問い合わせフォーム、またはTwitterにてご連絡いただけると助かります。
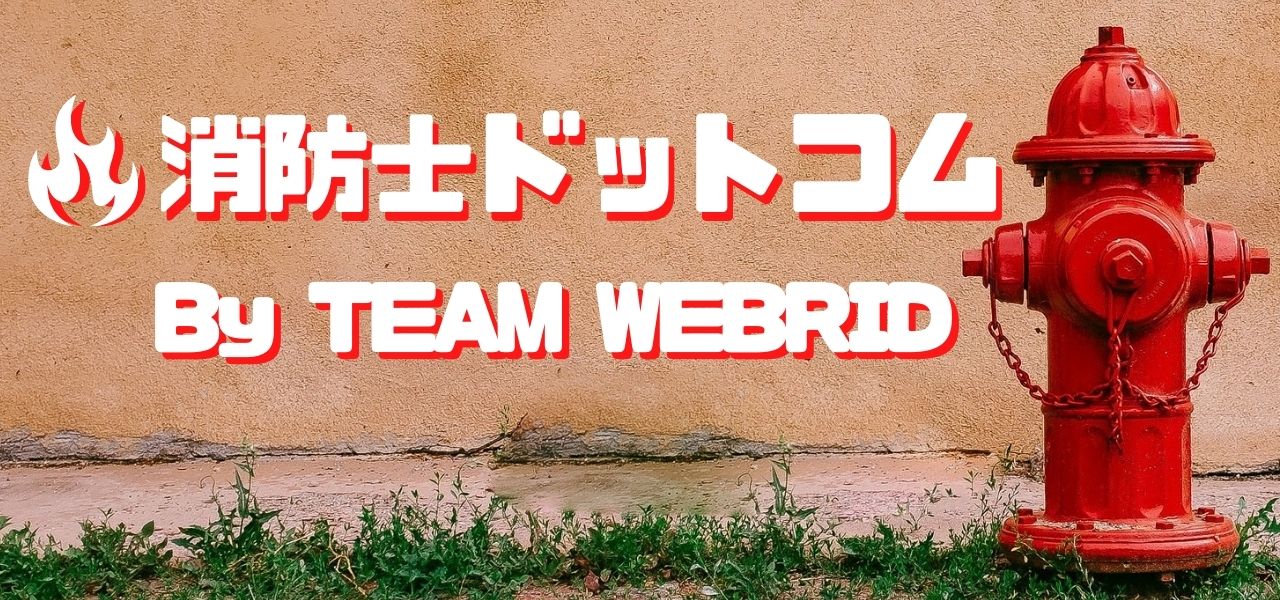

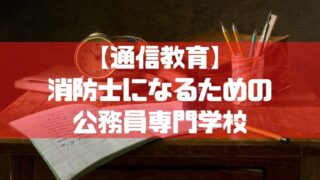







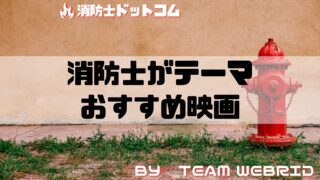


の違い-320x180.jpg)















コメント