消防士という職業は、多くの人にとって憧れの存在です。しかし、消防士になるには、どのような条件が必要なのでしょうか?また、消防士の出世コースや階級の上がり方は、どのように決まるのでしょうか?
この記事では、日本の消防士の出世コースと階級の上がり方について、大卒と高卒の違いを中心に解説します。また、階級の名前や順位だけでなく、組織の中での役回りや、呼び方、昇任試験についてもレポートします。
今回の記事も、現役消防士の方や消防職員OBの方々からの調査結果をもとにレポートしたいと思います。消防士になりたい人や、消防士のキャリアに興味がある人は、ぜひ参考にしてください。この記事を読むことで、消防士の階級や、消防の世界のことにもっと詳しくなれるでしょう。
消防士の階級の種類とそれぞれの役割

消防士の階級は上から順に
と分かれています。通称で通っている「消防士」というのは、階級の一つの名称です。消防士の階級は、大きくグループ分けすると以下のように分かれています。
消防士の出世コースは、大きく分けて、現場主体のコースと、内勤(日勤)主体のコースがあります。現場主体のコースは、初級職から中級職に昇進し、消防隊の隊長や副隊長を務めるコースです。内勤(日勤)主体のコースは、中級職から上級職に昇進し、消防署長や消防長を務めるコースです。
それでは、一つずつ上から順に解説していきます。
消防士の階級:消防総監
日本に1人しかいません。東京消防庁の消防長です。日本消防長会の会長など、さまざまな充て職を担うことになります。
消防士の階級:消防司監
政令指定都市の消防長です。政令指定都市とは、人口が50万人以上の都市をさしています。現在、全国で20都市が政令指定都市に指定されています。また、消防総監が消防長である東京消防庁においては、消防司監の階級で本部(本庁)の「部長」を務めています。
消防士の階級:消防正監
消防監の1つ上の階級であり、中核市クラスの消防長の階級になります。中核市とは、人口が20万人以上の都市をさしています。規模の小さい消防本部だと、階級自体が存在しません。消防吏員の数が200人以上又は人口30万人以上の市町村の消防長 です。
政令指定都市クラスだと、「部長」や「次長」「室長」と呼ばれる役職を担うことになります。東京消防庁では、「方面本部長」や「消防学校長」などの役職を担います。
消防士の階級:消防監
消防司令長の1つ上の階級です。消防監の階級で、消防長に就任する本部があります。規模の小さい本部だと、階級自体が存在しません。消防吏員の数が100人以上又は人口10万人以上の市町村の消防長 です。
「参事」「副参事」「部長」「室長」「次長」「課長」「課長主幹」「消防署長」など、本部の規模や特色により呼び方も変わっています。大隊長、署の隊長、指揮隊長を担う階級になります。
ほとんどが、毎日勤務をするようになり、火災現場に出動するのは、消防署の「署長」ぐらいで、本部付けの「参事」「副参事」「部長」「室長」「課長」「課長主幹」などは、災害現場に出向くことはありません。
ただ、消防署長が火災現場に出向くことは稀なことです。東京消防庁では、「本庁課長」「消防署長」「消防学校副校長」などの役職を担います。
消防士の階級:消防司令長
消防司令の1つ上の階級になります。具体的には、消防吏員の数が100人未満かつ人口10万人未満の市町村の消防長です。 規模の小さい本部だと、消防司令長の階級において、消防長に就任することもあります。
中核市以上では、「課長」「課長主幹」「副署長」「分署長」と呼ばれます。1つ上の消防監の階級が、消防長を担うような規模の本部では「参事」「次長」などと呼ばれます。中隊長から大隊長クラスの役割を担います。
他の階級でも説明しているとおり、職員数が500人程度の中核市の司令長と、職員数が1万8千人を超えるような東京消防庁の消防司令長では、もちろん職務の重さが違ってきます。中核市では、交代勤務を行う係の中で、一番上の階級となり、当直長(泊まり掛けで24時間体制の勤務を行う中で一番偉い人)を担うことになります。
この階級のあたりから、毎日勤務の比率が増えてきます。東京消防庁では、「方面副本部長」「消防署課長」「分署長」などを担います。
消防士の階級:消防司令
消防司令補の1つ上の階級になります。消防士長になってから、5年から10年ほどで昇任試験の機会が訪れるようです。規模の小さい本部だと、消防司令補試験はあるけど、消防司令試験はないという本部もあります。
「係長」「補佐」「課長補佐」「主幹」など、組織の規模や風土によって呼び方は様々です。小隊長や中隊長を務めるようになります。一定の係のリーダーを任されたり、1つ下の階級の消防司令補が束ねるグループを複数管理するようになります。
消防士の階級:消防司令補
消防士長の1つ上の階級になります。消防士長になってから、5年から10年ほどで昇任試験のチャンスが与えられます。規模が小さい本部では、昇任試験がない本部もあります。中規模の本部では、消防司令補から管理職とする本部もありますが、少数派となっています。
この階級のあたりから、小隊長扱いとなる本部が多く、「主査」「主任」「係長」「所長」(署長ではなく、出張所の長という意味での所長です)などの役職名がつく本部もあるようです。このあたりも、本部の規模により呼び方も立場も異なるようです。
ある程度責任のある仕事を任されるようになったり、企画の実働部隊としての責任者を務めたりするようになります。一定の規模のグループのリーダーを務めることになります。
消防士の階級:消防士長
消防士たちの兄貴分的存在になります。「副主任」などと呼ばれる本部もあります。本部によって異なりますが、採用されてから5,6年から10年ぐらいをめどに消防士長昇任試験に該当し、試験を受けることができます。
規模の小さい本部だと、昇任試験がなく、年功序列や個々の能力により昇任します。昇任試験を受ける年数に、相当な幅があるように感じるかもしれませんが、次のような理由のためです。
採用時の年齢が相当違う
一番若いと18歳(高校を卒業したばかり)、逆に年配組では30歳付近の年齢制限ギリギリで採用される職員もいます。
本部の規模により階級の幅がある
小さい本部だと、消防司令長が消防長(消防本部のトップ)というところもあれば、政令指定都市のように消防司監が消防長の本部もあります。消防司令長と消防司監だと、階級に3つの差があります。3つの差というと、消防司令長から下に3つは消防士長になります。
つまり、小さい本部では、消防人生40数年をかけて、消防士から消防司令長まで4回の昇任(副士長を含めると5回)をして、組織のナンバー1になるのに対し、大きい本部では、消防人生40数年をかけて消防士から8,9回の昇任を経験し、組織のナンバー1になるわけです。この意味がわかれば、小さい本部と大きい本部で昇任試験までの年数に違いが出るのも納得できます。
\消防本部の大きさの違いについてはこちらの記事/
話がそれますが、消防業界には、全国の消防長が集まる消防長会という仕組みがあります。
全国の消防長が集まるわけなので、高い階級の職員ばかりかが集まってるかと思いきや、前述のように消防総監を筆頭に、3つ4つ下の階級の職員まで入り混じっているという状況になります。
消防士の階級:消防副士長
消防士の1つ上の階級になります。消防副士長になるには、昇任試験を受ける本部とそうでない本部が混在します。小規模な本部では、昇任試験を受け、消防副士長の経験を積みます。しかし、一定の職員数がある本部では、消防士から直接消防士長への昇任試験を受けることが一般的です。
昇任試験を受けなくても階級って上がるの?と思うかもしれません。消防副士長に自動的に階級が上がる場合、消防士を10数年以上務めている場合がほとんどです。言い換えると、消防士長への昇任試験に合格できない、又は意図的に合格しようとしない職員がほとんどです。
ここまで言えば、消防職員の中でも、消防副士長がどういう目で見られる存在か、どういう立ち振る舞いをしている存在か、汲み取ってもらえると思います。そのため、テレビのニュースなどで消防職員の不祥事に関するニュースで
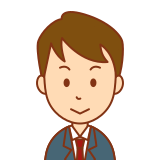
○△◇市消防局の、50代の消防副士長が、、、、
などのニュースを耳にすると

うんうん、わかるわかる、やっぱりね。
と納得できることがあるようです。
消防士の階級:消防士
消防職員として採用されたら、みんなこの階級からスタートします。どんなに大きな消防本部の消防長でさえ、スタートは消防士です。大学院を卒業してから採用されたとしても、最初は消防士です。
採用後に、消防士としての基礎を学ぶ消防学校へ、初任科教育を受けるために入校しますが、この時も消防士の階級として入校します。
\消防学校についてはこちら/
一番下の階級なだけあって、現場活動においても一番下働きを求められます。上司や先輩たちの指示通り動くことが重要であり、個人の判断で何かを行うことはほぼありません。階級が一番低いだけに、職員数も一番多い階級です。
縦社会では、立場が上位になればなるほど存在数が減っていきますが、消防士の階級の世界でも同じです。階級が上位になればなるほど、職員数も減っていきます。責任のある仕事はまだ与えられません。役職等はもちろんなく、一般的な係員となります。
\消防士になるための採用試験に関する情報はこちら/
消防士の階級や昇任は給料や年収にどれぐらい影響するの?

消防士といえども、大きなくくりでは地方公務員であり、条例に定められた給料表に基づき、基本給が定められています。階級が上がることと、給料が上がることは、必ずしも直結しません。一般的な給与を定める条例だと、1年間で4号給ずつ昇給します。

階級が上がったから、今年の昇給は10号給アップ!!
だなんてことはありません。コツコツと毎年4号級ずつ給料表を上がっていきます。ただ、この給料表というものが一定の幅ではないため、4号給の昇給で5,000円しか上がらない年もあれば、10,000円上がる年もあります。
このあたりの違いは、それぞれの本部の条例で定まっていますので、消防本部が属している市町村のホームページで確認することができます。気になる人は、調べてみてください。非常に難解な書き方がされていて、よくわからないと思います。
\消防士の給料についてはこちら/
消防士の階級や昇任について高卒と大卒で同級生だとどれぐらい差があるの?

一般の会社や、社会通念上の常識で考えると、同級生で考えた場合、高卒程度の方が、4年間早く消防職員になったからといって、大卒程度の方が早く昇任すると思いますよね。しかし、消防職員ではそうでないことがあります。
例えば、消防士で採用された後、消防士長に昇任するための試験と、消防司令補に昇任するための試験しか、昇任試験が実施されない本部を例にしてみます。
高卒ですぐ消防職員になった場合(18歳)、最短で消防士長になるのには9年かかり、27歳で消防士長になります。その後、消防司令補になるには、最短で10年かかり、37歳で消防司令補になります。
大卒ですぐ消防職員になった場合(22歳)、最短で消防士長になるのには7年かかり、29歳で消防士長になります。その後、消防司令補になるには、最短で8年かかり、37歳で消防司令補になります。
高卒の場合、昇任試験に必要な年数が9年、10年との設定に対し、大卒は、7年、8年と、学歴による昇任試験に必要な経験年数の優遇があります。しかし、消防司令補に昇任するタイミングは同じ37歳になっています。学歴による優遇年数が少ないために、学歴による昇任の差がなくなっています。
消防士の職務の性質上、学歴よりも、職務の経験をいかに多く積んでいるかということを重視し、さらには、先に採用された絶対的立場である先輩後輩の逆転現象が起きることを控え、縦社会の秩序を守ることも重要視されています。
\消防士の世界の上下関係の現実はこちらの記事/
✔️消防学校とは ✔️初任科の内容 ✔️初任科のカリキュラム ✔️初任科の準備(荷物編) ✔️初任科の準備(暗記編) ✔️初任科の準備(事前勉強編) ✔️初任科(勉強以外) ✔️初任科以外の入校
消防士の階級について昇任試験って難しいの?

昇任試験では、
など、かなりの広範囲を試験の対象としています。また、知識を問われるだけでなく、「訓練礼式」と呼ばれる規律訓練の実技を行う本部もあるようです。
【解説】消防士の階級や昇任って高卒と大卒でどれぐらい影響あるの?のまとめ

消防士の階級について、説明してきました。階級ごとの意味や役職について、しっかり理解できたと思います。階級と給料が直結していないのは、意外でしたね。昔ながらの公務員の世界で言われる”年功序列”の影響が残っているものと推測されます。
今後も、新しい情報が入り次第、レポートを更新していきます。
この記事を読まれた方で、さらに詳しく知りたいことがあれば追跡調査しますので、コメントか問い合わせフォーム、またはTwitterにてご質問ください。
また、消防関係者の方で、うちの本部ではこうなってるよ、それは違うんじゃない?などのご意見をいただける際も、コメントか問い合わせフォーム、またはTwitterにてご連絡いただけると助かります。
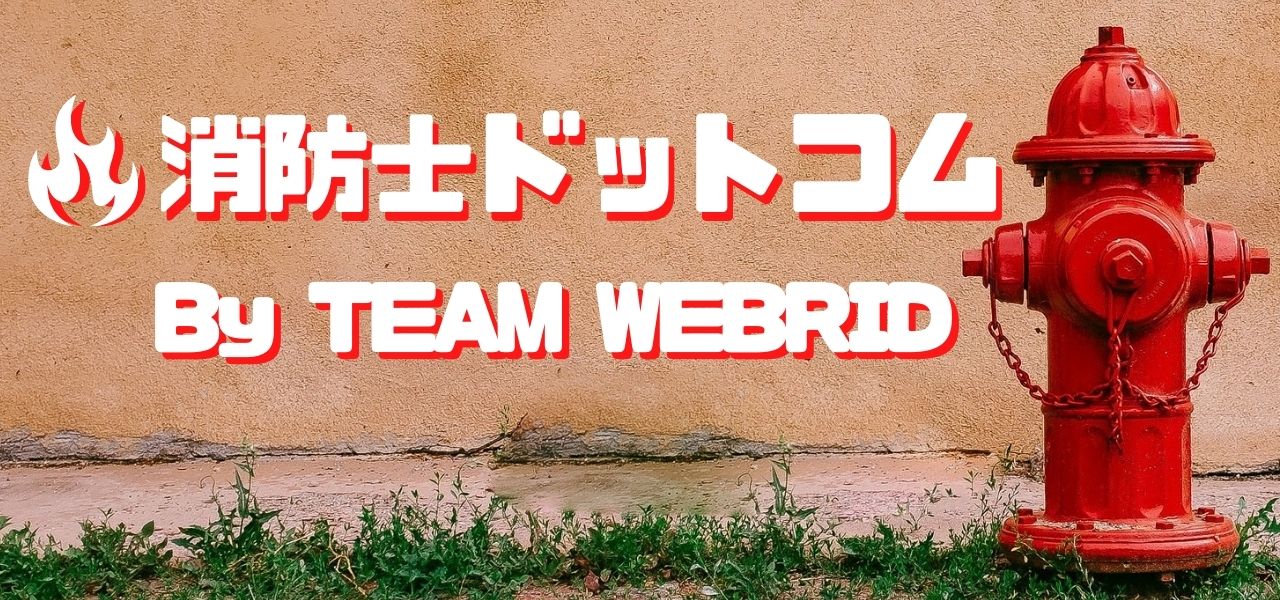

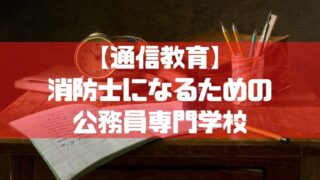







の違い-320x180.jpg)

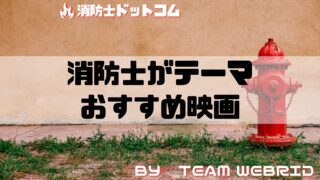











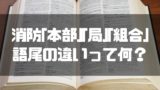




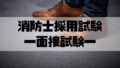

コメント