こんにちは、TEAM WEBRIDです。今回のテーマは懸垂。消防士といえば懸垂です。ロープを昇る、引く、結ぶ、何をするにしても、懸垂に必要な筋肉は優先して身につけるべきもの。そのため、消防士採用試験の体力試験では、懸垂を試験科目に組み込んでいる消防本部がほとんどです。
今回の記事も、現役消防士や消防職員OBへの取材をもとに解説します。この記事を読むことで、懸垂の回数を伸ばすコツが理解できます。それではレポートします。
懸垂のトレーニングができる環境について

懸垂の回数を伸ばすには、懸垂をやらないという選択肢はありません。身近なところで、無料で懸垂ができるのは次のようなところ。
・公園の鉄棒
・公園のぶら下がり健康記器具
・公園のうんてい
・公園のサッカーゴールの枠
有料となれば、もちろんスポーツジム。スポーツジムにも種類があります。
・昔ながらのスポーツジム
・パーソナルジム
・24時間空いている無人ジム
自宅でも懸垂はできます。できますが、懸垂器具はさまざまです。
・引っ掛けるタイプ
・突っ張るタイプ
・自立型
トレーニングに最も必要なことは、継続です。つまり、継続しにくい環境でのトレーニングを始めても、継続できずに途中でやめてしまう可能性があります。
例えば公園での懸垂について。家の近くに懸垂のできる鉄棒があったとします。あったとしても、多少のストレスが生じます。なぜなら懸垂をするために、着替えて、靴を履いて、歩いて公園に向かい、人目を気にして懸垂を行い、家に帰ってきます。この行為を継続するためには、それなりの覚悟や決意がないと難しいのではないでしょうか。
次に、スポーツジム。こちらも公園と同様に、わざわざ時間と手間をかけて出向く必要があります。ただ、例えば学校と自宅を結ぶ経路にスポーツジムがあるとか、職場と自宅を結ぶ経路にスポーツジムがある人は、継続しやすいかもしれません。となると、残る問題点は有料だということ。筋肉を手に入れる代わりにお金をどんどん失い続けます。
このような状況を踏まえると、懸垂の回数を伸ばすのに最も適した環境は、やはり自宅です。
なお、現役消防士は職場でみっちり懸垂ができています。
自宅での懸垂は、家から出ないため、着替える必要もありません、裸でも大丈夫です。懸垂するまでの時間も数秒です。公園やジムまで歩いていく必要はありません。公園で人目を気にする必要もないし、ジムで筋肉自慢達の中で劣等感を感じる必要もありません。タイミングも無限大。寝起きや寝る前でもへっちゃらです。ただでさえ、継続性の難しい筋トレ、できるチャンスは多い方が良いに決まってる。
懸垂を行う場所は自宅の一択となりましたが、では懸垂器具は何が適しているのでしょうか。順番に説明します。ますは、引っ掛けるタイプ。引っ掛けるタイプの人気ナンバー1はこちら。
ドアのような形状にガコンと引っ掛けます。引っ掛けるだけで懸垂バーの出来上がり。設置は超簡単。
ですが、気になるデメリットが何点か。まず、ドアなどの引っ掛け先が傷みます。固定具合が弱い物であれば、設置部分がバタつき傷だらけに。固定がしっかりしているものであれば、強度を心配すべきです。そもそも懸垂を行うような想定で設置されたわけではありません。
懸垂のように、全体重や勢いによる加重がかかると、次第に破壊してしまうのがオチです。賃貸ならば、引き払う際の敷金からごっそり抜かれ、持ち家ならばそれなりの修理代がかかってしまいます。また、高さ的な問題も。自宅の中で、懸垂器具を引っ掛ける部分というのはある程度限られてしまいます。
背が高い人にとってはなおさらです。せっかくぶら下がっても、足が床に着いてしまうようだとトレーニングはしづらくなります。懸垂を行ったことがある人はわかると思いますが、足を曲げたままの懸垂ってしんどいんですよ。初心者は挫折するのが目に見えています。結論、おすすめできるものではありません。
次に突っ張るタイプ。先ほどの引っかけるタイプより、さらにコンパクトです。突っ張るタイプの人気ナンバー1はこちら。
こちらの最大のデメリットは、安心感がないこと。いつポロッと外れて大けがをしてしまうかわかりません。もちろん、引っ掛けるタイプ同様に、設置した部分が傷むことはもちろんですが、高さはそれ以上に低くなってしまいます。安物買いの銭失いとはまさしくこのこと、次第に使わなくなるのが目に見えています。
最後に自立型。もうこれ一択です。間違いない。自立型は人気タイプがいろいろ。こんなのや。
こんなのも。
メリットたくさん。まず、家が傷まない。
「床が傷むじゃん。」
いえいえ、床にはつなぎ合わせが可能ジョイントマットを敷くだけでノーダメージです。
高さも問題なし。もちろん背が低い人でも簡単に届くように高さ調節可能。そして抜群の安定感、安心して全力で取り組めます。逆にデメリットはというと、先に説明した引っ掛けるタイプ、突っ張るタイプに比べて高価。そして、でかい。高価なものは仕方がない、だって物が良いんだもの。でかい?いやいや、格好良いの間違いじゃないですか?部屋にこんなの置いてたら懸垂ができるだけじゃなく、インテリアとしてもかっこよすぎる。女の子が部屋に来ても
「すごーい!!」
とぶら下がるの間違いなし。話がそれたので元に戻します。”懸垂の回数を伸ばす環境を作る”ということを最優先で考えた場合、自宅に自立式の懸垂台を購入するのが間違いありません。実際、マッチョ関連のYouTnubeやSNSを見てください、みんな自宅に自立式の懸垂台を持っています。安物買いの銭失いになって損しないように気をつけましょう。
懸垂の回数を伸ばすトレーニングについて

それでは、懸垂ができる環境が整ったところで、具体的なトレーニングについて説明します。トレーニングなので、現在の懸垂レベルによってトレーニング内容が違ってくるのは当然のこと、ここでは3つの段階に分けて説明します。
21回以上できるような人はこの記事は読んでいないはずなので、省略します。ちなみに、消防士採用試験の体力試験で懸垂が15回から20回もできれば満点です。なお、ここでの回数とは、肘を伸ばしきってぶら下がった状態から、顎(あご)が鉄棒のバーを完全に越えるまで体を引き揚げて1回とカウントします。
「1回ならできる」
と言っている人、最初の1回、ジャンプして鉄棒に飛びついた勢いのまま、体を引き揚げて1回とカウントしていませんか?それは0回です。
0回から5回の人向け懸垂の回数を伸ばすトレーニング

0回から5回の人、懸垂素人レベルの人たちですね。学生時代、それなりに運動部に所属していて運動に自信がある人でも、懸垂をしたことがない人であれば、このあたりの懸垂レベルでもおかしいことはありません。運動部であれば、練習中にミニゲームのペナルティなどで腕立て伏せを行うことはあっても、ペナルティで懸垂を行うことはありませんからね。
「腕立てふせならいくらでもできるのに、懸垂がぜんぜんできない。」
よくある話です。結局のところ、懸垂には懸垂用の筋肉が必要なわけです。このような人たちは、まずは懸垂に慣れることですね。1回もできない人のトレーニングは2つ。1つ目は、持久懸垂。
ジャンプして鉄棒にぶら下がり、そのまま耐える。きつくなるまでぶら下がる。きつくなったら降りる。これを3セット。インターバルはぶらさがった時間と同程度。具体的にはこれ。
これで1セット。5分休憩。次のセット開始。
2つ目は、ジャンプして鉄棒に飛びつく。そこからゆっくり、できるだけ長い時間をかけてひじを伸ばす下がり懸垂です。ひじが伸びきったら着地。これを5回連続。5分休憩。これで1セット終わり。これを3セット。
どちらか1つでもいいし、両方やってもいい。これを3日に1回行えば、一カ月(30日)後には10日行えます。懸垂に必要な筋肉について、超回復を10回も繰り返せば、どんな人でも最低1回は懸垂ができるようになります。
筋肉は、疲労により筋肉繊維が断裂します。断裂した筋肉繊維は、断裂から2日程度かけて回復する際に、従前の筋肉繊維より太くなって回復します。これを超回復といいます。この仕組みが、筋力トレーニングにより筋力がアップする原理です。ちなみに、筋肉痛とは、筋肉繊維が断裂したことで起こる痛みです。
注意点が1つだけあります。それは、1日のトレーニングが終わった翌日、筋肉痛が起きているかどうかということ。筋肉痛が起きていないということは、筋肉繊維の断裂が起きていません。つまり、超回復が起きないので懸垂回数が伸びるわけがありません。筋肉痛が起きなかったということは、
ということが考えられます。ぶら下がる時間を伸ばしたり、下がり懸垂の回数を増やしたりすることが必要です。最低限、筋肉痛が起きるまではトレーニングの負荷をあげることを考えてください。筋肉痛さえ起きてしまえばこっちのもの、二日間かけて超回復により筋肉繊維のパワーアップを待ちましょう。
次に懸垂が1回でもできる人。肘を伸ばし切った状態から、1回でも顎(あご)が懸垂バーを越えるまで体を持ち上げるパワーがあるなら、顎(あご)が懸垂バーを越えなくてもいいので、5回懸垂をしてください。つまり、正しくない懸垂を5回してください。正しくないとは、肘を伸ばし切らず、顎(顎)が懸垂バーを越えない懸垂です。正しくない懸垂を5回。これを3セット。
2セット目、3セット目は5回できないかもしれません。2セット目に3回しかできなかったら、1回着地してからでもいいので、残りの2回を実行してください。要は、休憩しながらでもいいので、正しくない懸垂でいいので、5回×3セットこなしましょう。
この場合も同じく、翌日に筋肉痛が起きるかどうかがポイントです。もしも筋肉痛が起きなかった場合は、回数を増やすか、正しくない懸垂を正しい懸垂に近づけてください。つまり、今の懸垂より、もっと肘を伸ばす、もっと顎(あご)を懸垂バーに近づける。
これも3日に1回で大丈夫です。あいだの2日は超回復です。3日に1回超回復が起きれば、だんだんと正しい懸垂ができる回数も、2回、3回と増えていきます。がんばりましょう、トレーニングを継続し、超回復を繰り返すことで確実に回数は伸びます。
6回から10回の人向け懸垂の回数を伸ばすトレーニング

5回到達おめでとうございます。ここまでできるようになれば、体つきも少し変わってきます。脇の下に膨らみが出てくるはずです。広背筋と呼ばれる筋肉です。お風呂に入る前に、鏡の前に立つのも楽しくなってくるかもしれません。
ここからは、トレーニングによる筋力アップだけでなく、懸垂に関するコツも追加します。まずはトレーニング。非常にシンプル。限界まで、正しい懸垂をやりましょう。そしてインターバル。長めにとりたいところ。3分から5分はとりたいですね。2セット目。同じく限界まで攻めましょう。そしてインターバル。3セット目。同じく限界まで。
これで翌日、筋肉痛にならないようであれば、限界まで懸垂ができてないということ。自分に甘いタイプだと認識しましょう、あなたの限界はもう少し先です。しんどいなと思っても、そこからもう1回できると信じて踏ん張ってください。
次に懸垂に関する知識です。肝心なのは2つ。1つ目。力を入れる指の意識。力を入れるのは、外側の3本だけです。
「いやいや、左右合わせて指6本で体持ち上げるより、指8本の方が絶対力入りそう」
こんな声が聞こえますが、そんな素人考えをぶち破る理由はこれ。消防士の手です。

外側3本の付け根には豆ができているのに、人差し指の付け根には、豆がまったくありません。つまり、懸垂バー握った時に、力が入っていないということです。実際に懸垂をやってみるとわかるのですが、確かに外側の指3本を意識した方が、力が入りやすいのがよくわかります。
2つ目。体の持ち上げ方について。一般的な懸垂は、”体を腕で引っ張って持ち上げ、顎の位置が懸垂バーを越える”というイメージだと思います。
しかし、消防士の懸垂は違う。”胸を懸垂バーに引き寄せる”というもの。持ち上げるのではなく、引き寄せる。胸を懸垂バーに引き寄せたら、自然と顎が懸垂バーを越えている、というもの。つまり、上半身は胸を反ったスタイルになり、自然と顔が天井を向くことになります。マッチョ系YouTubeを見てみてください、みんな体が弓のように後ろに沿っています。限界までのチャレンジと、コツを活かすことで、最高回数10回を目指してください。
11回から20回の人向け懸垂の回数を伸ばすトレーニング

このレベルになってくると、もう一人前です。20回を目指して、各自それなりの自分に合ったトレーニングが見えてくるでしょう。ここではあえて、1つのトレーニングパターンを説明します。
まずは目標回数を設定します。ここまで来たならば、欲を出して、20回を目指しましょう。目標を20回とします。
1セット目。限界までチャレンジ。14回できたとします。着地します。
インターバルを極力短くします。5~10秒。
そしてすぐ開始。目標回数20回までの残り回数、6回を目指します。限界までチャレンジした後なので、3回しかできません。それでOK。着地します。
インターバル5秒から10秒ですぐさま再チャレンジ。残り3回こなします。これで1セット完了。
つまり、目標回数を続けてできないにしても、最短時間で目標設定の20回をこなすわけです。
2セット目までのインターバルはしっかりとって大丈夫です。5分程度でしょうか。
残り2セットも同様にこなしましょう。連続してできないにしても、最短時間で目標回数をこなします。このトレーニングを、超回復を経験しながら3日に1回行えば、確実に限界回数は伸びていきます。
その先に少しだけ触れときます。20回以上の懸垂回数を目指すのであれば、負荷を高める必要があります。つまり、ウエイトを身にまとい、体重を意図的に増やすということ。これを行えば、ウエイトを外した時の体の軽さのおかげで回数が伸びていくわけです。このレベルは、消防士採用試験ではオーバースペックのレベルです。
✔️消防学校とは ✔️初任科の内容 ✔️初任科のカリキュラム ✔️初任科の準備(荷物編) ✔️初任科の準備(暗記編) ✔️初任科の準備(事前勉強編) ✔️初任科(勉強以外) ✔️初任科以外の入校
なぜどのレベルのトレーニング方法も3セット必要なのか

懸垂の回数を伸ばすトレーニングについて説明しました。どのトレーニングにおいても、3セットを推奨しています。どうして3セットなのかというと、最低3セットは同じトレーニングを行わないと、筋肉繊維の断裂が起こるまでの負荷を与えることができないからです。
筋肉は、人間の脳から指令が出て動きます。このとき、司令塔である脳は筋肉に対して100%の能力を発揮するような指令は出しません。リミッターを効かせている状態です。なぜなら、常に100%の能力を発揮していたら、筋肉繊維の断裂ばかり起きてしまい、継続的な作業ができません。また、ケガや故障の原因になりかねません。
そのため、通常は筋肉の上限にゆとりをもったままトレーニングをしていることになります。つまり、余力を残した状態で1セット程度トレーニングを行ったところで、筋肉繊維は断裂せず、超回復にはつながらないわけです。余力を残した状態でのトレーニングであっても、脳の指令が出せる上限まで3セット以上同じ負荷を繰り返せば、筋肉繊維の断裂から超回復につなげることができます。
具体例として、火事場の馬鹿力という逸話があります。
これは、江戸時代、家が火災になった人が、通常時じゃ到底持ち上げることさえできないようなタンスを担ぎ上げて逃げ出したという話。普段はリミッターが効いて、体を壊さないようにしている脳の指令も、火災という非常事態、さらにはこのままだと財産(江戸時代はタンスひとつに財産が詰まっている)が失われてしまうという危機感が合わさり、100%、もしくは100%以上の指令を出しています。
ちなみに、逃げ出した後は、腰が砕けたように倒れこみ、数日間寝たきりになったとかどうとか。そりゃそうですよね、通常は出さない力を出したわけだから、体の部位を痛めたり、立ち上がれないほどの全身筋肉痛に見舞われたりして当然です。
他にも、オリンピックで見かける重量挙げの選手なども同じようなことが言えます。競技の寸前に、大声を出したり、顔をビンタしたりしていますよね。あれは、気合いを入れるという意味、集中力を挙げるという意味のようにも解釈されますが、脳から出る信号のリミッターを可能な限りはずしにかかっているという意味もあります。
話がだいぶそれましたが、トレーニングによる筋肉繊維の断裂を引き起こすには、最低3セットはトレーニングが必要です。
懸垂による体への効果は消防士になれるだけじゃない

消防士になるための懸垂トレーニングについて説明してきましたが、懸垂による体の変化についても説明しておきます。懸垂によるトレーニングは、懸垂の回数が伸びるだけじゃありません。先にも述べましたが、広背筋が広がり、理想のスタイルと呼ばれる逆三角形の体型に近づきます。
また、実は腹筋も鍛えられ、俗に言うシックスパックに近づけます。なぜかというと、懸垂のように体を持ち上げたり、懸垂バーに胸を近づけたりするような動きでは、腹筋が大きく影響します。意外ですよね。
「どうして腹筋が?」
と思うかもしれません。しかし、これは消防士の経験則から理解できます。定期的なトレーニングを欠かさない消防士ですが、時には一定期間、トレーニングができない日々もあります。そんな時、久しぶりに懸垂を行うと、翌日には腹筋も筋肉痛になるそうです。この事実自体が、懸垂には腹筋が必要ということを物語っています。考え方によっては、懸垂の回数を伸ばすために、腹筋も並行して鍛えるという作戦も有効です。
消防士の体力試験|懸垂の回数を0から伸ばすコツのまとめ

消防士採用試験の体力試験において、懸垂の回数を伸ばすためのトレーニングについてレポートしました。まとめると、次のとおり。
「筋肉は正直だ。」
「筋肉は嘘つかない」
このような名言があるぐらい、筋肉は努力により誰でもパワーアップが可能です。こちらの記事でも説明していますが、体力試験は足切りです。
5回以上できれば、懸垂を理由に落とされることはありません。消防士といえど、あくまでも公務員、受かるためには勉強です。こちらの記事で自分のレベルを判断してください。勉強が苦手という人は、まずは公務員専門学校の無料パンフレットからスタートするのが賢い選択です。1年を棒に振ると、400万ぐらい損しますから。
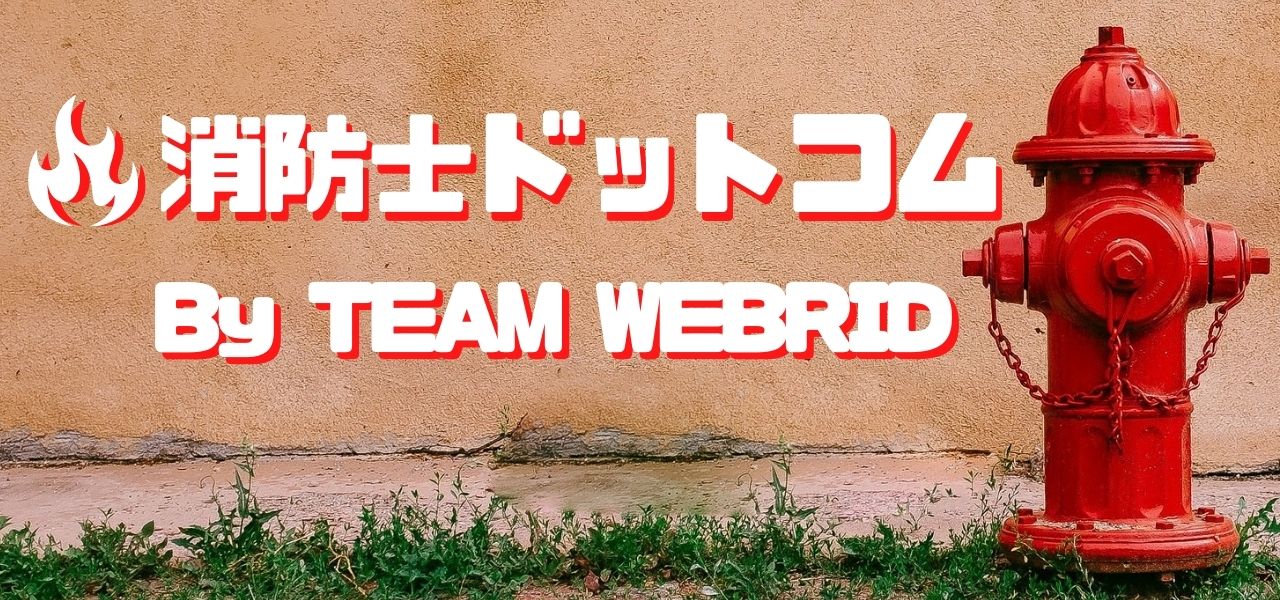

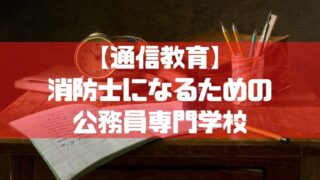















の違い-320x180.jpg)


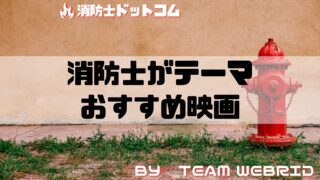

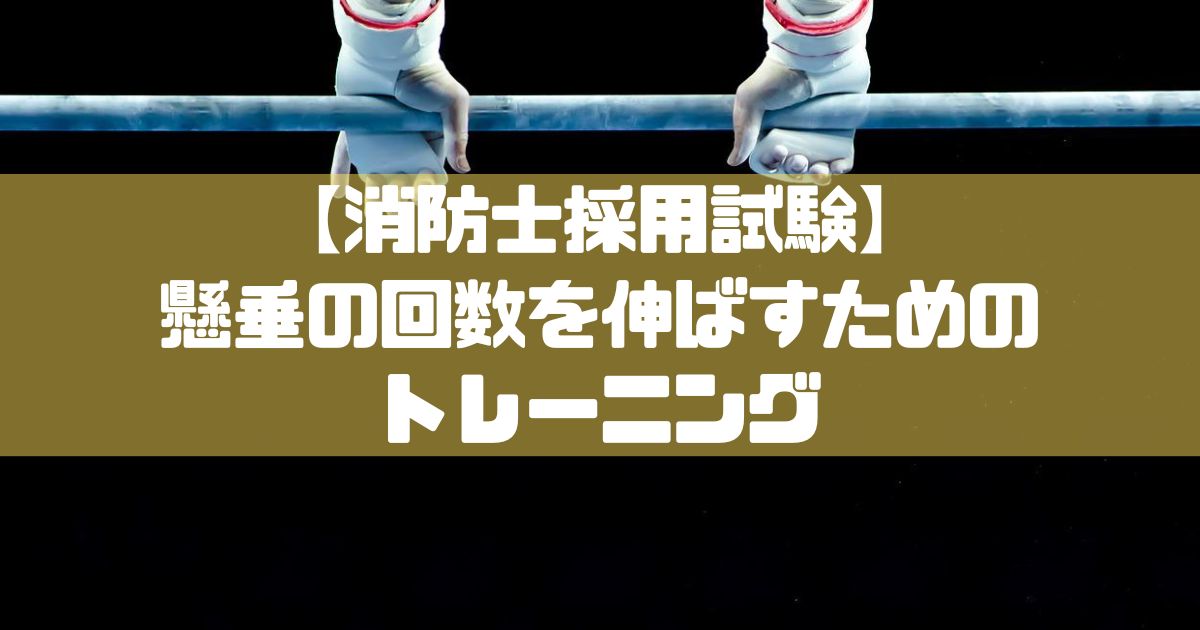

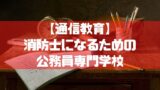
は事実なのか?-120x68.jpg)

コメント